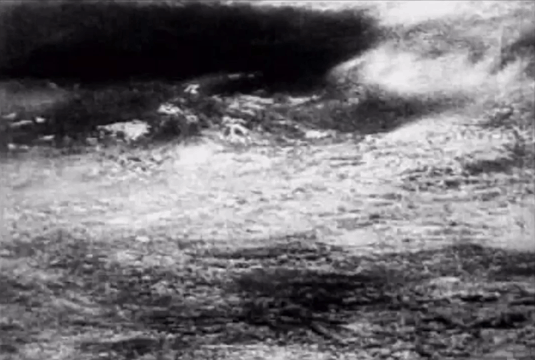⋯⋯いずれにせよ、「シーニュ」、「シニフィエ」、「シニフィアン」という三つの語彙がきわだたせる言語記号の定義が、ソシュール自身にとっての不幸にとどまらず、いまやその決算期にさしかかりつつある二〇世紀的な「知」の体系が蒙りもした最大の不幸なのもかしれぬという視点が、しかるべき現実感を帯び始めているのはまぎれもない事実だといわねばならない。(蓮實重彦『「魂」の唯物論的擁護にむけて ――ソシュールの記号概念をめぐって』「ルプレザンタシオン」第五号所収 1993年)
以下、蓮實重彦1993におけるソシュールと星雲をめぐる記述をまず掲げる。
⋯⋯⋯彼(ソシュール)は、体系化されることのない積極的な差異なるものを明らかに知っている。「混沌たる塊」や「星雲」といった比喩で語っているものこそがそれでなければならない。そこには、体系化されることのない積極的な差異としての言語記号が無数におのれを主張しあうことで、カオスと呼ばれるにふさわしい風土を形成している。ソシュールが裸の言語記号を思考することを断念せざるをえないのは、そのひとつひとつが「イマージュ」を身にまとうことをひたすらこばみ、素肌のままであたりを闊歩するという野蛮さに徹しているからだ。これはなんとも始末におえない世界だとつぶやきながら、彼は思わず目を閉じ、耳を覆わざるをえない。
その瞬間、ソシュールの不可視の視界には、不在を告げるものとしての「イマージュ」をまとった「シーニュ」と、その体系にほかならぬ「ラング」とが、同時に音もなく浮上することになるだろう。『一般言語学講義』と『原資料』とに詳細に書き込まれているはずでありながら、「シーニュ」としてはそのように読まれることをこばんでいるのは、体系化されることのない積極的な差異の世界から体系化された否定的な差異の世界へのソシュールの余儀ない撤退ぶりにほかならない。ソシュールを読むにあって見落としてはならぬ肝心の記号は、おそらく、この差異の領域を隔てている差異をひそかに不在化してしまった「イマージュのソシュール」の身振りをめぐるものだろう。それは、差異に言及しようとするまさにその瞬間、それをすぐさま否定的なものだと定義せずにはおれず、差異の肯定を進んで放棄してしまうソシュールに対する『差異と反復』のジル・ドゥルーズの苛立ちを招いた身振りにほかならない。(⋯⋯)
フェルディナン・ド・ソシュールが明らかに知っていながら、それに言及することを避けることしかできなかったふたつの差異を隔てる不在化が、いたるところで思考から記憶を奪い、その活動を鈍らせてゆく。仮にポストモダンと呼ぶものが話題になりうるとしたら、あたかもこの不在化が自然な事態だといわんばかりに思考が受け入れている記憶喪失による活動の純化をおいてはないだろう。近代化された「観念論」ともいうべきこうした風潮の中でひたすら鈍り行く思考は、二つの差異の間の差異を知っていたことの痕跡さえとどめぬ「イマージュ」の世界のみを視界に認めているが故に、かえってすべてがすがすがしく冴えわたっているかの錯覚と戯れることができる。ひろく共有されているこの錯覚に対する闘いが、複数性の擁護として闘われなけれなならないことを、ソシュールは少なくとも自覚していた。だが、それに続くものとして形成された二〇世紀の「知」の体系のほとんどは、その自覚からの余儀ない撤退を、あたかも自然なこととして容認してしまっている。
その容認を自然なものとしては容認せずにおくこと。それが、ソシュール以後に生きるものたちの思考の身振りでなければならない。「魂」の唯物論的な擁護がいささかの倒錯性も身にまとうことなくいま始まろうとしている。(蓮實重彦『「魂」の唯物論的擁護にむけて ――ソシュールの記号概念をめぐって』「ルプレザンタシオン」第五号所収 1993年)
ここでの核心は、ソシュールの《体系化されることのない積極的な差異の世界から体系化された否定的な差異の世界へのソシュールの余儀ない撤退ぶり》である。
ラカンは逆の動きをした。《無意識は言語のように構造化されている》(体系化された否定的差異の世界)から、「言存在は、言語のように構造化されていない」(体系化されることのない積極的な差異の世界へ)と。
ラカンは “Joyce le Symptôme”(1975)で、フロイトの「無意識」という語を、「言存在 parlêtre」に置き換える remplacera le mot freudien de l'inconscient, le parlêtre。…
言存在 parlêtre の分析は、フロイトの意味における無意識の分析とは、もはや全く異なる。言語のように構造化されている無意識とさえ異なる。 ⋯analyser le parlêtre, ce n'est plus exactement la même chose que d'analyser l'inconscient au sens de Freud, ni même l'inconscient structuré comme un langage。(ジャック=アラン・ミレール、2014, L'inconscient et le corps parlant par JACQUES-ALAIN MILLER )
※この言存在は、言語ではなく、ララング(言葉の物質性)の審級にある(参照:ララング定義集)。さらにいえばララングとは、ドゥルーズ&ガタリのリトルネロの審級にある。
リトルネロとしてのララング lalangue comme ritournelle (Lacan、S21,08 Janvier 1974)
ここでニーチェの考えを思い出そう。小さなリフレインpetite rengaine、リトルネロritournelleとしての永遠回帰。しかし思考不可能にして沈黙せる宇宙の諸力を捕獲する永遠回帰。(ドゥルーズ&ガタリ、MILLE PLATEAUX, 1980)
ミレールは2005年のセミネールで、「言存在」概念をふくめて次のように図式化している。
もっともーー、フロイトの「無意識」をラカンは「言存在」に置きかけたとミレールは言っているがーー、実はフロイトにも二つの無意識がある。力動的無意識とシステム無意識である(参照:非抑圧的無意識 nicht verdrängtes Ubw と境界表象 Grenzvorstellung (≒ signifiant(Lⱥ Femme))。これは一般にはほとんど知られていないが、フロイトの叙述に何度も現れる。
かつまたフロイトには、精神神経症と現勢神経症概念がある。
現勢神経症 Aktualneurose の症状は、しばしば、精神神経症 psychoneurose の症状の核であり、そして最初の段階である。(フロイト『精神分析入門』1916-1917)
これもそれぞれ精神神経症が力動的無意識、現勢神経症がシステム無意識にかかわり、後者の現勢神経症はーーわたくしの知るかぎりでだがーー日本では中井久夫が何度も取り上げている(参照)。
力動的無意識が「自由連想」に馴染む(通念としての)「無意識」であり、フロイト派臨床では長い間これが主だった。だが現在、「自由連想」は実質上、お釈迦の時代である(参照:「幻想の横断」・「自由連想」・「寝椅子」のお釈迦)。
いまはこれについてはもう触れない。ここでは、力動的無意識が「言語のように構造化された無意識」、システム無意識が「言語のように構造化されていない無意識」である、そのことだけを強調しておくだけにする。
フロイトは、「システム無意識あるいは原抑圧」と「力動的無意識あるいは抑圧された無意識」を区別した。
システム無意識は欲動の核の身体への刻印であり、欲動衝迫の形式における要求過程化である。ラカン的観点からは、まずは過程化の失敗の徴、すなわち最終的象徴化の失敗である。
他方、力動的無意識は、「誤った結びつき eine falsche Verkniipfung」のすべてを含んでいる。すなわち、原初の欲動衝迫とそれに伴う防衛的エラヴォレーションを表象する二次的な試みである。言い換えれば症状である。
フロイトはこれをAbkömmling des Unbewussten(無意識の後裔)と呼んだ。これらは欲動の核が意識に至ろうとする試みである。この理由で、ラカンにとって、「力動的あるいは抑圧された無意識」は無意識の形成と等価である。力動的局面は症状の部分はいかに常に意識的であるかに関係する、ーー実に口滑りは声に出されて話されるーー。しかし同時にシステム無意識のレイヤーも含んでいる。(ポール・バーハウ、2004、On Being Normal and Other Disorders A Manual for Clinical Psychodiagnostics)
⋯⋯⋯⋯
以下、冒頭に戻って、日本においてソシュールをめぐり、どういうことが言われてきたかについての重要だと思われる文を掲げる(もちろんわたくしの知る限られた範囲である)。
丸山圭三郎派の幼稚なカオス概念……つまり言語的に分節化されない一様な混沌がカオスだと言うなら、もちろんそのようなカオスはドゥルーズにはない。むしろ、カオス―――少なくとも内在平面においてとられられたカオスは、それ自体、とことん差異化=微分化されていて、さまざまな特異点がひしめいている。そのようなものをカオスと呼ぶなら、それは潜在的多様体として存在する。 (浅田彰発言『批評空間』1996Ⅱー9 共同討議「ドゥルーズと哲学」)
たとえば「シニフィアンとシニフィエの絆は、ひとが混沌たる塊に働きかけて切り取ることの出来るかくかくの聴覚映像とかくかくの観念の切片の結合から生じた特定の価値のおかげで、結ばれる」とソシュールが書くとき、その「混沌たる塊」こそ、現前化しつつある差異の立ち騒ぐ領域なのである。ソシュール自身のよってときにカオスとも呼ばれ、丸山圭三郎がイェルムスレウの術語の英語訳としてのパポートを採用しているものにも相当するこの「混沌たる塊」は、しかし、『ソシュールの思想』の著者が考えているように、分節しがたいものの不定形なマグマ状の連続体といったものではない。たしかにソシュール自身もそうした誤解を招きかねない「星雲」といった比喩を使ってはいるが、あらゆるものがもつれあっているが故にそれがカオスと呼ばれるのではなく、そこにあるすべての要素がそれぞれに異なった自分をわれがちに主張しあっているが故にカオスなのである。
なるほど、一見したところそこには秩序はないが、しかし、秩序はそこからしか生じえないはずのものであり、これを「コスモス=分節化されたもの」と「カオス=分節化以前のもの」の対立としてとらえるかぎり、作家としてのソシュールが視界に浮上する瞬間は訪れないだろう。「作家」とは、みずからを差異として組織することで「作品」という差異を生産するものだからである。もちろんこの差異はコスモスには属していない。(蓮實重彦『「魂」の唯物論的擁護にむけて――ソシュールの記号概念をめぐって 丸山圭三郎の記憶に』1993年)
マルクスがいう「社会的関係の隠蔽」は、一般に、物象化として、すなわち本来関係的なものが実体化されることとして理解されている。そんなことなら、マルクスでなくても他の人でもいえるだろう。さらに、たとえば、言語にかんして、それが、本来差異的な関係体系(分節化)なのに、物象化されて、世界が“実体的に”そうであるかのようにいられるというたぐいの批判も、それと同じことである(丸山圭三郎)。
ここから一つの“根源的な”批判と治療法が提起されてしまう。だが、それらの理論こそ“社会性”の隠蔽である。われわれは、遡行すべき、共同主観的世界も、分節化をこえた連続的・カオス的世界ももたない。それらは、言語ゲームの外部にあるがゆえに無意味であるか、またはそれ自体言語ゲームの一部にすぎない。それらはたんに物語として機能する。(柄谷行人『探求Ⅰ』1986年)
⋯⋯⋯⋯
※付記
上に一部を引用したが、『「魂」の唯物論的擁護にむけて』全文を掲げておこう(以前に既に数度引用したものである)。
慎重さの放棄
かねてから言語学の術語の曖昧さに深い苛立ちを覚えていたフェルディナン・ソシュールは、なんとか誤解を避けようとして傾けられたはずの厳密な語彙の模索にもかかわらず、結局のところ、その努力が自分に慎重さの放棄を促すしかないというならそれはそれで仕方がないがと諦めきったかのように、いささか唐突ながら、言語記号に「シーニュ」signeという名前を与えることを提案する。
「シーニュ」とは、それが指し示している対象に与えられた名前ではなく、「シニフィエ」signifiéと「シニフィアン」signifiantというふたつの異なる心的な要素の相互的な依存関係においてのみ、記号として機能するものだというのがその提案の内容である。言語記号としての「シーニュ」が、ときに「聴覚映像」と訳されもする「音のイマージュ」と「概念」と呼ばれたりする「思考のイマージュ」との恣意的な結びつきにほかならぬといった事実を、ここで改めて指摘するには及ぶまい。もちろん、このような定義によって確定された言語記号としての「シーニュ」が、「ラング」langueと呼ばれる言語記号の体系の単位なのである。この提案のなされた日付が一九一一年五月十九日のことであることもよく知られているし、そのとき、ソシュールが、ジュネーヴ大学の「一般言語学」講座の担当教授として、三年目の講義を行っていたことさえ、いまでは周知の事実である。
では、こうしたソシュールの提案がいくぶんか慎重さを欠いた行為だったとも受け止められかねぬというのは、いかなる意味においてであるか。もちろん、記号一般が「シーニュ」と呼ばれるのは、フランス語を母語として操るものにとってごく自然な事態だとまず指摘しておくべきだろう。だが、ソシュール自身は、言語記号をも「シーニュ」と呼ぶことにいくぶんかのためらいを感じており、のちにみるごとく、それ以外の語彙によるさまざまな命名の試みを行っていたのである。「シーニュ」を構成するかたちで相互依存の関係にあるふたつの心的な要素「シニフィエ」と「シニフィアン」についても、また同様である。問題は、ジュネーヴ大学での「一般言語学」の講義が三年目に入った一九一一年五月十九日に改めて提案された三つの語彙の間に、いかにも厳密すぎる形式的な秩序が存在していることにある。つまり、「シーニュ」とは、「意味すること」を意味するフランス語の動詞「シニフィエ」signifierに対応する名詞にほかならず、その動詞の過去分詞にあたる「シニフィエ」signifiéと、現在分詞にあたる「シニフィアン」signifiantとが、いわば名詞化されたかたちで、それを構成するふたつの心的要素を意味する語彙として選ばれているのである。日本語の訳語として、ときに「シニフィエ」が受動的に「意味されるもの」、「シニフィアン」が能動的に「意味するもの」とされるのも、同じ動詞の過去分詞と現在分詞という対立が前提とされていることによる。
ところで率直にいって、この命名法はあまりにも形式的に完璧すぎる。「シニフィエ」と「シニフィアン」との関係はあくまで「恣意的」なものだという注釈をあからさまに嘲笑するかと思われるほど、あらゆる恣意性の概念を排除するかたちで互いに緊密に対応しあっているからである。こうして、この三つの語彙を口にするものたちに過度の安心感を与えかねないほどみごとな形式的秩序が成立してしまった結果、ソシュールが構築せんとしつつある科学としての「言語学」のイメージがいささか平板化され、言語を思考しようとするものが陥らざるをえない深い諦念に対する感受性が、あらかじめ断たれてしまうことになる。あるいは、そのことによって、今日、ソシュール理解のひとつの潮流を形成しつつある「言語学批判」の実践者という立場が、視界に鮮明な輪郭を結ばなくなってしまう危険があるといってもよい。
事実、ソシュール自身、そうした危険には充分に自覚的であったはずであり、手稿のまま残された厖大な『原資料』(それが異る段階をへて徐々に人目に触れるようになった事情はここでは詳述しない)にあたってみればそれはあまりに明らかだとする視点もたしかに成立する。丸山圭三郎の先駆的な業績『ソシュールの思想』に刺激されて活気をおびた日本派「ソシュール」研究の系譜につらなる研究者たちに、そうした傾向は著しく顕著である。実際、彼らは、『一般言語学講義』のそれではなく、『原資料』のソシュールを解読しながら、『《力》の思想家ソシュール』(立川健二)を擁護したり、『沈黙するソシュール』(前田英樹)について語ったりしており、そこに、傾聴に値する議論が展開されていることはいうまでもない。にもかかわらず、『講義』と『原資料』との差異を超えたかたちで、「シーニュ」、「シニフィエ」、「シニフィアン」という語彙で言語記号の特性を提示しようとするソシュール像というものがまぎれもなく存在しており、そうした肖像の成立に手をかすことになったソシュール自身の慎重さの欠如が、『原資料』の詳細な解読によって救われるとは到底思えないのである。
もっとも、そのとき書物を執筆していたわけではないソシュールにとって、講義中に口にされたこの「シーニュ」の定義など、いつでも訂正のきくとりあえずのものだったのかもしれない。にもかかわらず、彼の弟子たちのノートをもとに編纂された『一般言語学講義』の肝心な部分で、「シーニュ」は「シニフィエ」と「シニフィアン」という二つの要素の緊密な結合だと説かれることで、あたかもそれが、久しく続けられていた言語記号の定義の試みの最終的な形態であるかのように受け取られてしまう。なるほど、死後出版としての『講義』が刊行されてから半世紀ほどたってようやく出版されることになったいわゆる『原資料』を念入りにひもといてみれば、こうした「シーニュ」の定義があえて修正されねばならぬ理由など、いささかも存在していないことは明瞭である。それがどのような語彙で呼ばれることになろうと、ソシュールにとっての言語記号の概念はあくまで一貫しているからである。
なるほど、ソシュールが一九一一年五月十九日の定義に落ち着くまでに、語彙の上でいくつかの躊躇や逡巡を示していた事実を跡づけられぬわけではない。「シーニュ」に到達する以前に、「セームséme」が言語記号にふさわしい語彙として考えられていた時期があったと指摘することは極めて容易だからである。「シーニュ」の一語が体系性を欠いたもろもろの「しるし」をも意味しうるのと異なり、「セームは体系に属し、シーニュの二項が一体化した全体、つまり記号であり同時に意味であるものをあらわす」とあるとおり、それはあくまで「ラング」という体系の単位とみなされているし、読まれるとおりそのときでも、「セーム」が、ものの名前を指示する記号ではないという姿勢は一貫している。また、「シニフィエ」と「シニフィアン」についても、「ソンson(=音声)」と「サンスsens(=意味)」を初めとして、いくつもの対立的な語彙が提案されては修正されている。しかも、「ソン」が物理的な音でも生理学的な声でもなく、ごく抽象的な「音のイマージュ」にほかならず、また、「サンス」にしても、いわゆる意味ではなく、あくまで「音のイマージュ」に対応すべき「概念」、すなわち「思考のイマージュ」であるとする視点は確実に維持されているのである。つまり、そのいずれもが、一九一一年五月十九日に提案されたとされる「シーニュ」、「シニフィエ」、「シニフィアン」とほぼ同じ内容を示しているのだから、この点に関するかぎり、講義中にノートをとっていた弟子たちは、師の考えをいささかも誤解しもしなかったし、歪曲してもいないということができる。言語記号の定義についてみるならば、『一般言語学講義』も『原資料』もほぼ同じことを述べており、『原資料』ばかりが特権視されねばならぬ理由はまったく存在していない。事実、『一般言語学講義』の第一編「言語記号の特質」の冒頭に、「われわれは概念と聴覚映像との結合を記号と呼ぶ」という言葉が読まれる。それに続いて、聴覚映像のみを「記号」と呼ぶ一般的な了解とは異なり、「われわれは、記号という語を、総体を示すためにとっておき、概念と聴覚映像とを、それぞれ『シニフィエ』と『シニフィアン』に変えることを提案する」と書きつがれており、「シニフィエ」と「シニフィアン」とを結びつけるのは恣意的な関係であるという指摘も、その直後にみられるものだ。
たとえば、「シーニュ」、「シニフィアン」、「シニフィエ」という三つの語彙による言語記号の定義に到達する以前に、ソシュールは、純粋に心的なものと定義される「聴覚印象」というものが、「ラング」は恣意的なものだとはいえ、発音にあたっては肉体器官の意志的な使用を前提とせざるをえない以上、はたしてその物理的かつ生理的な条件から独立したかたちで充分に定義しうるものであろうかと自問自答している断章が存在する(ノート「3305.7」)。そこでの彼は、言語記号の定義に必要とされるのが、人類に普遍的にそなわっている言語事象の運用能力だとする立場に立っている。実際、アルファベットの[L] の音と[r]の音とを区別するにあたってギリシア人はいかなる理論など必要としてはおらず、ごく自然にその「差異」を識別していたというのである。つまり、「聴覚印象」に従ってしか器官の意志的な使用はありえないがゆえに、精神にもたらされる「聴覚印象」を誰もが「確実かつ明瞭に」確定可能だとされているのだ。そう述べてから、言語記号は「観念」Idéeと「音」Phonismeとの結びつきではないと指摘し、いわゆるソシュール的な記号の定義を図解することになる。
そこで提起された図を言説化するなら、まず、「記号の領域」というものが設定され、それに「心理的」という説明が括弧で示される。その領域は二分され、「聴覚映像」と「思考の映像」が併置され、その関係が「心的結合」であると改めて指摘されている。さらに、「聴覚映像」の部分から直線が伸び、「発音行為」という言葉につながっており、また「思考の映像」から伸びる直線は、「聴覚映像を反復する……ための発音行為」という語群に直結しているのである。
「シーニュ」、「シニフィエ」、「シニフィアン」という語彙は使用されていなくても、この図式をかたちづくる諸要素が、一九一一年五月十九日の言語記号の定義にかさなりあうことはほぼ明らかである。「聴覚映像」という言葉は『一般言語学講義』にも姿をみせており、それを「シニフィアン」と呼ぶのだと提起されているから誤解の余地はなかろうし、『講義』では「シニフィエ」と呼ばれることになる「概念」が、ここではいまだ「思考の映像」という説明にとどまっている点に関しても、さしたる問題はなかろうと思う。にもかかわらず、「ノート」における記述と『講義』のそれとになんらかの違いが識別しうるとしたら、それは、言語記号を「シーニュ」と呼ぶことで、ソシュールがそれまでくりかえして試みてきた語彙の模索に終止符をうち、以後、注釈を放棄しているかにみえることにつきている。
これは、予想される以上の大きな差異をかたちづくることになる。というのも、「言語学者」フェルディナン・ソシュールが蒙った最大の不幸は、言語記号を「シーニュ」と呼び、それが「シニフィエ」と「シニフィアン」との結合からなるとしたことで、彼の言語理論における「記号」の概念が決定的な輪郭におさまったかのごとく信じられても不自然ではない状況が、客観的に成立してしまったからである。彼がいったん構想されもした『書物』を完成させず、また『一般言語学講義』を自分の手で刊行しなかったのは、その言語記号の定義をめぐる躊躇や逡巡が、論理的な完璧さを実現しえぬことの苛立ちによるものではなく、その完璧さが保証するかもしれない「言語学」の体系化が、みずからの意図とは気の遠くなるほど距ったものであることに充分自覚的だったからである。
いま「みずからの意図」と呼んだものが、具体的にどんなものであるかの詮索は別の機会に譲ることにする。だが、いずれにせよ、「シーニュ」、「シニフィエ」、「シニフィアン」という三つの語彙がきわだたせる言語記号の定義が、ソシュール自身にとっての不幸にとどまらず、いまやその決算期にさしかかりつつある二〇世紀的な「知」の体系が蒙りもした最大の不幸なのもかしれぬという視点が、しかるべき現実感を帯び始めているのはまぎれもない事実だといわねばならない。事実、「シーニュ」、「シニフィエ」、「シニフィアン」という三つの用語は、命名者ソシュール自身の思惑を遥かに超えた頻度で、言語学の音韻論的な領域はいうまでもなく、文化人類学から精神分析学にいたるまで、この上なく便利な概念として、ありとあらゆる領域に身軽な流通ぶりを誇っている。
こうした隣接の学問領域に流通している記号の概念の多くが、ソシュールとはむしろ無縁なものだと判断することは決してむずかしくない。たとえばジャック・ラカンが「シニフィアン」の優位を口にするとき、それはソシュール的な記号の概念とはいささか異なるものだし、また、クロード・レヴィ=ストロースの「神話素」といった概念もまた、ソシュールその人にとってはむしろ消極的な意義しか担っていない音韻論に、多くのものを負っているはずである。さらには、「シーニュ」の定義が、とりわけ「シニフィアン」をめぐって、それが物理的かつ生理的な音であると主張されたりするように、ときに信じがたい誤読の対象にするなっていた事実を指摘することさえ、いまではむしろ容易なのである。
だが、優れて大胆な思考の身振りを演じてみせたものにはしばしば起こりがちなこうした読み間違いが、言語学の領域でソシュールの思想の正しい継承をさまたげていることの不幸をいまさらいい募ってみても始まるまい。問題は、ソシュール自身が、ある種の諦めから慎重さを放棄することで引き寄せてしまった「言語学」的な身振りそのものの不幸の質を吟味することにある。それは、まさしく「シーニュ」の定義そのものに露呈されている言語記号を思考することの不可能性という不幸にほかなるまい。
その不幸とは、言語について思考しようとするソシュールが、とりわけ言語記号をめぐって行う言表行為のあらゆる水準で絶えず向かい合うことになった不幸である。科学としての言語学の成立に不可欠な要素としての不幸だとさえいってよかろうと思うが、「シーニュ」、「シニフィエ」、「シニフィアン」という三つの語彙で言語記号を定義しなければならなくなったとき、充分に意識的だったはずの不幸を、わずかなりとも軽減しようとする誘惑に、ソシュールが思わず屈してしまっているかのようにみえる。ここでの定義が、いくぶんか慎重さを放棄することでえられたものだと冒頭でいっておいたのも、そうした意味においてである。また、なにがしかの諦念が彼に不幸と直面することを延期させたのではなかろうかという想像も、そうした事態に由来するものだ。いま、その不幸について論じるべきときがきているように思う。
イマージュのソシュールとソシュールのイマージュ』
すでに触れたことだが、『一般言語学講義』のテクストと『原資料』の記述との微妙な差異を超えたかたちで、言語記号を「シーニュ」、「シニフィエ」、「シニフィアン」という三つの語彙で定義したソシュール像というものがまぎれもなく存在する。そうした肖像におさまるソシュールを、とりあえず「イマージュのソシュール」と名づけることにしよう。あるいは、そこに「ソシュールのイマージュ」と呼ぶにふさわしい肖像が成立するのだというほうがより正確かとも思うが、いったん不幸に顔をそむけることで言語記号の定義が可能となったとするなら、「イマージュのソシュール」にはある種の楽天性がたちこめているといえるかもしれない。あるいは、それがある諦めからでた振る舞いだとするなら、ことによるとペシミズムが色濃く漂っているというべきなのかもしれない。いずれにせよ、かかる肖像が、『原資料』を詳しく読みとき、さらには後期の「アナグラム」をめぐる彼の言説と親しく接することで成立するソシュールの全体像といったものによって修正さるべきか否かといった論議は、このさい無視することにする。理由は、それがソシュールであれ誰であれ、必ずしも一貫した言説を担い続けていたとはいいがたいひとりの作家を前にした場合、そのさまざまな発言の矛盾を弁証法的に統合することで、そこに初めてその“正しい”「全体像」がかたちづくられるはずだといったたぐいの議論など、にわかに信じることはできないからである。
それが誰であれ、ひとつの存在は、決って複数の異なる肖像のもとで視界に浮上する。言語的な事象もまた、そのような複数の表情におさまることで思考を刺激するものだが、しかるべき目的の遂行にあたって、そうした肖像や表情のいくつかをとらあえず無視するという態度は、当然のことながらいくらでも可能である。というより、思考というものは、そのようにしてしかしかるべき事態を厳密な対象としてとらえることはできないはずなのだ。事実、ソシュール自身にしても、言語がまとう複数の表情のいくつかを自覚的に排除するという方法的な選択によって、かろうじて言語記号の定義にたどりついたにすぎない。
丸山圭三郎にならって、そうした手続きを「記号論的な還元」と呼ぶべきか、あるいは『グラマトロジーについて』のジャック・デリダとともに、「音声的質料の還元」と呼ぶべきかという問題はさして重要ではない。ここでなにより重要なのは、言語記号を「シーニュ」と呼ぼうと提案するソシュールが、言語そのものではなく、なによりもまず、言語の「イマージュ」を視界に浮上させようとしているという事態にほかならない。そのとき、彼は、言語と無媒介的に接することを断念しているのだが、それは『一般言語学講義』のテクストからも、『原資料』の文章からしても明らかである。たとえば、「言語は形態formeであって、実体substanceではない」、あるいは「言語には差異しかない」といった記述を『一般言語学講義』に読むときひとはなにを想像することができるか。さらには、「aはbのたすけがなくてはなにも示すことができない。あるいは、ふたつはたがいの差異によってしか価値を持たないと言ってよい。……価値はあの永遠の差異の茂みにあるだけだ」といった記述を『ノート』のひとつに読んだりする場合、なにを想像することができるか。かろうじて想像しうるのは、「実体ではない」といわれる言語記号としての「シーニュ」の徹底した不在である。「シーニュ」とは、それと現実に接することで思考されるものではなく、それと接したことの刻印を介して初めて思考可能になる対象だといわれているからである。「思考の映像」としての「シニフィエ」と「聴覚映像」としての「シニフィアン」との心的な結合によって成立するのだという「シーニュ」は、そもそもの始まりからして「イマージュ」としてしか思考の対象となりがたいものだったはずなのだ。しかも、「シーニュ」が言語記号として単独に意味作用の形成に貢献するのではなく、それ自体として「実体ではない」はずの差異によってしか意味が生成しないというのだから、ここでの「シーニュ」の不在は二重化されているといわねばなるまい。こうして、ソシュールは、言語そのものではなく、「イマージュ」としての言語を、「イマージュ」を介して思考するという姿勢を選択したことになるのである。そして、そうした選択をしたことの意味はきわめて重い。
もちろん、「イマージュ」を介して言語を思考するという自覚的な選択が、彼自身にどんな試練を課すことになるか、ソシュールは充分に心得ていたはずである。それが彼の真意であるか否かはひとまずおくとしても「イマージュのソシュール」は、言語をひとまず「体系=システム」として思考せざるをえない状況に自分を追いやっているのであり、そのとき形成されるのが「ソシュールのイマージュ」というひとつの肖像にほかならない。「ソシュールは『システムと構造』の思想家ではない」という立川健二の言葉にもかかわらず、言語記号を「シーニュ」と呼ぼうと提案するソシュールは、その当然の帰結として、「体系」としての言語を思考しなければならないからである。そして、誰ひとりとして、その事実を否定する権利を持ってはいない。
確かなことは、言語記号を「シーニュ」として定義するソシュール像の形成を、それが形成されようとするその瞬間に、ソシュール自身がことさら妨げようとしていないというという事実である。ある種の諦念からそうするほかはなかったのだろうというのはひとつの解釈にすぎないが、その解釈が正当化されうる文脈をソシュールは明らかに準備しているようにみえる。にもかかわらず、ここでのソシュールが、慎重さを放棄することで、不幸を軽減しようとしているという事実は厳然として残る。つまり、「イマージュ」としての言語を選ぶことで、彼は、言語とともにある状態からいったん自由になり、距離のかなたにしりぞいた言語をめぐって、つまりはその不在の「イマージュ」に向けて思考を投げかける権利を行使することになったのである。
こうした選択が、ソシュールにとって可能であったはずの数ある選択のひとつにすぎないと主張することは難しい。現存としての言語とともにある限り、その「体系」を思考することはいうまでもなく、その単位を確定することさえ不可能だからである。かれには、そうすることしかできなかったのだ。であるが故に、「イマージュのソシュール」が導きだす「ソシュールのイマージュ」を否定するのは無駄ないとなみというほかはない。われわれの興味は、なぜソシュールが、あれほど形式的に整いすぎた「シーニュ」、「シニフィエ」、「シニフィアン」という三つの語彙で言語記号の定義を行い、そのことで、それ以前の躊躇や逡巡の跡を抹殺しようとしたのかという心理的な理由の詮索にはない。問題は、言語を思考するものとして、彼が不断に向かい合っていたはずの不幸から、ここでいったん顔をそむけることになったという事実そのものである。「イマージュとしてのソシュール」とはそのようにして成立するひとつの肖像にほかならないが、そうした肖像によって触発される「ソシュールのイマージュ」がどんな輪郭におさまっているのかを真剣に考えてみなければならない。
「イマージュのソシュール」によって成立する「ソシュールのイマージュ」は、たとえば丸山圭三郎のように、後期のアナグラム研究に着目しながら、「乗り越えるための記号論」をソシュールが準備していたと指摘することで回避できる程度のものではないし、また、立川健二のように「《力》の思想家」としてのソシュールを擁護することで回避できる程度のものでもない。「イマージュのソシュール」なるものは、そうした指摘と擁護とはおよそ無縁の領域に、あるいは、ことによるとそうした読み方となんら矛盾することなく、「言語学」的な思考とは異なる力に支えられたかたちでそびえているのかもしれない。
もちろん、「ソシュールのイマージュ」などというそんな肖像など初めから存在しており、いまさら驚くにはあたらないとする視点も存在する。たとえば、「『記号』でも『形態』でもいいが、これは『観念』と『音』とがどこからやってきて結びついた結合体ではない」と書き、「ソシュールは結合の事実など信じてはいない」と小気味よく断言する『沈黙するソシュール』の前田英樹は、「結合の事実など一度もなかったのだ。あるのは、『記号』がそういう抽象的要素に分解されることができるという事実だけだ。……ただ『記号』というひとつの経験、『音』にも『観念』にも似ていない『記号』という具体的な経験があるのだ」と続けることで、誰もが多少は胡散臭い思いをいだいたことのある「シニフィエ」と「シニフィアン」の問題に、あっさり決着をつけてしまう。
ことによると、こうした立論は決定的に正しいのかもしれない。「ソシュールが『音』や『観念』やそれらの結合について語るのは、むろん言語学が、あるいはそれが基礎とする形而上学が、そういう記号の操作としてしか成りたたないからだ」と前田英樹がいうとき、彼は「イマージュのソシュール」を当然の前提としているかにみえるからである。だが、「実体」substanceという語彙の導入をめぐって、そもそも言語学が形而上学の内部にしか成立しえないという事実を、みずからこしらえあげた装置によって言語学者たちに向ってあらかじめ示す目的があったのだと彼が論を進めるとき、われわれはそこに姿をみせる意識されざる思考のニヒリズムといったものに、思わずたじろがざるをえない。いったい、ソシュールは、いわゆる『原資料』の草稿類を埋めつくしたあれだけの言葉を、もっぱら無自覚な他人に事態を認識させるために、しかも、おのれにとってはあまりに当然すぎる事実をあえて書いていたとでもいうのだろうか。
たしかに、ソシュールの思考の中で、言語記号たる「シーニュ」の「イマージュ」や、その体系としての「ラング」といった「イマージュ」があっさり形成されてしまうかにみえるとき、そこに「形而上学」的な何かが顔をのぞかせている事実を否定するのは難しい。また、そうならざるをえないことの成り行きに充分自覚的だったソシュールが、科学としての「言語学」の完璧な成立をできれば遅延させたいと願っていたというのならまんざらわからぬでもない。だが、「草稿が示しているのは、記述のための基礎原理といったものではない。それは、どんなときでも『語』や『単位』や『記号』や、その他もろもろの言語学の言葉に対する注釈的延期として現れる」と書き、さらに「彼がひたすら希望していたのは、ラングの学としての<言語学。に厳密な言説をおくりこむこと、ただそれだけだ」とも述べている著者が、ことソシュールの思考の「形而上学」的な側面に触れたときばかりは、いかにもニヒルな語調で、それが同時代の言語学者たちに対して示す一種の戦術的な態度にすぎぬと断じたりしているのは自家撞着もはなはだしく、理解に苦しむといわねばならない。
おそらく、ソシュールの読み手として決して資質を欠いているわけではない一人の研究者が、不意に意識されざるニヒリズムに陥ったりしてしまうのは、前田英樹が、これという根拠も示さぬまま、「彼が草稿のなかで際限なくただひとつのことを書き」続けていたのだと冒頭から断定していることに由来している。だが、あえていうまでもあるまいが、人は、決して「ただひとつのこと」だけを書いたりはしない。事実、ソシュールは、多くのことがらを書き残しており、この当然の事態を認識することからすべての読みは始まらなければならない。そのとき、ソシュールになり代わって思考することをおのれに禁じるだけの慎しみを失わずにいることが、あらゆる書き手に求められるのは当然のことである。
すでに指摘したことだが、われわれがいう「イマージュのソシュール」とは、いくつも存在しているはずのソシュール像のひとつにすぎない。「イマージュ」を介してしか言語と言語記号とを思考しえないというその立場は文字通り「形而上学」的なものではあるが、そうあるしかないことの責任は、もちろんソシュールその人が引き受けているはずのものだ。事実、ソシュールは、いま形成されたばかりの「ソシュールのイマージュ」をさらに徹底させようとしているかにみえるのだが、そのことの意義にある程度まで自覚的ではあったろうと想像されはするものの、だからといって、彼が充分なまでに自覚的であったとは誰にも断言しがたいのである。
かくして、とりあえず形成された肖像としての「イマージュのソシュール」によって導きだされる「ソシュールのイマージュ」は、楽天的でもあれば悲観的でもあるという二重の相貌におさまることになるかにみえる。だが、より正確にいうなら、そうした「ソシュールのイマージュ」は、楽天的でもなければ悲観的でもないのである。問題は、むしろ、負の二重性ともいうべきその曖昧な風土に触れることで、言語を思考することに特有の不幸があっさり中和されてしまうという事実である。つまり、「シーニュ」、「シニフィエ」、「シニフィアン」という三つの語彙による言語記号の定義だけは断じて避けて通らねばならなかったし、それを避けて通ることもまた断じて許されないという苛酷な現実に直面していたはずのソシュールは、いつしか、そうした定義を試みてもよいし、また試みなくてかまわないといった二者択一を引き受けようとする余裕のある存在へと変貌しているのである。そのとき、不幸が思考の条件でなくなっているのはいうまでもない。
もっとも、こうした不幸の消失ぶりは、必ずしも思考の頽廃を意味するものではない。そのような事態が許されていないかぎり、ひとは絶えざる失語状態に陥るほかはないだろうし、また、ものを書くことも永遠に禁じられたいとなみでしかなくなってしまうだろう。それが、言語記号を思考するという体験と、書くという言語記号の実践とを隔てている微妙ではあるが決定的な違いなのである。
思考するという体験は、その対象がなんであれ、純粋に「イマージュ」の体験であり、とりわけ言語が主題となった場合、「イマージュ」にさからう体験として言語記号を書くこと、すなわちエクリチュールの実践とはいかなる意味のおいてもかさなりあうことがない。そこには、誰にも修正を施す術すらない偏差が横たわっており、「イマージュのソシュール」によって導きだされる肖像としての「ソシュールのイマージュ」は、まさしくその決定的なずれゆきによって支えられているものなのだ。
『一般言語学講義』が弟子たちの手で編まれた死後出版だという事実をいくぶん神話化するかのように、ある時期には間違いなく構想されていた書物の執筆を最終的に断念したことが、フェルディナン・ド・ソシュールを他の言語学者たちから隔てる決定的な優位なのだと論じたてようとするひとつの傾向が存在する。だが、いったんは書き始められた草稿を彼が完成させなかったことは、みずからの手で書物を刊行することがなかったことと同様に、とりたてて特筆さるべきことがらではない。ソシュールはまぎれもなく書くひととして生涯を終えており、その事実を否定するにたるものはなにひとつとして残されていないからである。事実、『原資料』の解読から始められた注目すべきソシュール研究のほとんどは、書かれたもの、すなわち彼のエクリチュールを読むことで成立しているのだが、丸山圭三郎の先駆的な著作が『ソシュールの思想』と題されており、『ソシュールのエクリチュール』でなかったことが象徴的であるように、その多くは、ソシュールの思考をエクリチュールを介して読みとることがごく自然に可能であるかのような視点をとっている。もちろん、それが絶対的に不可能だというつもりはないが、少なくとも、それを可能にするための方法が模索されていたという形跡はどの書物にも読み取ることはできない。ごく自然に書かれた言葉から出発していながら、そこには、書くという言語記号の実践と「イマージュ」の体験として言語記号を考えることの絶対的な偏差に対する戦略が徹底して欠けているからである。
ソシュールは「言語学者ではない。ソシュールは思想家である」といった立川健二の宣言が露呈させているのも、そうした戦略の欠如にほかなるまい。ソシュールが言語学者であろうが、思想家であろうが、そんなことはどうでもよろしい。だが、ソシュールが書くひとだったこと、つまり言語記号の実践者としての作家であったことだけは、誰も否定することはできまい。われわれの到達しうる「ソシュールのイマージュ」とは、まさしく作家としての、エクリチュールの人としての輪郭のもとに姿をみせる肖像にほかならない。
差異と力
作家としてのソシュールは、当然のことながら、いままさに自分がそれとともにあるはずの言語記号なるものを思考することの不可能性に逢着する。彼がかろうじて思考の対象としうるのは、まさしく現前化しつつある瞬間のそれではなく、いま、ここには不在であることのみを告げている「イマージュ」としての言語記号にすぎないからである。
だが、それは、いささかも驚くべき事態ではない。言語記号を「シーニュ」と呼ぶと提案し、「シニフィエ」と「シニフィアン」との恣意的な結合を生きるものだとされるその「シーニュ」が「ラング」という言語体系の単位だと定義しないかぎり、あたりに偏在する無数の言語記号の群れそのものは、たんなる無秩序のかたまりしかかたちづくることがないからである。そのときソシュールがいわんとしているのは、そうとは公言されていないものの、「シーニュ」という形式におさまろうとしないあまたの言語記号が、ひたすら差異化することしか知らない始末におえぬ差異にほかならないという事実をおいてほかにあるまい。つまり、現前化しつつある瞬間の言語記号そのものが差異なのであり、その作動中の差異を思考しようとする試みを彼があらかじめ回避しているのは、ごく当然の成り行きだといってよい。
たとえば「シニフィアンとシニフィエの絆は、ひとが混沌たる塊に働きかけて切り取ることの出来るかくかくの聴覚映像とかくかくの観念の切片の結合から生じた特定の価値のおかげで、結ばれる」とソシュールが書くとき、その「混沌たる塊」こそ、現前化しつつある差異の立ち騒ぐ領域なのである。ソシュール自身のよってときにカオスとも呼ばれ、丸山圭三郎がイェルムスレウの術語の英語訳としてのパポートを採用しているものにも相当するこの「混沌たる塊」は、しかし、『ソシュールの思想』の著者が考えているように、分節しがたいものの不定形なマグマ状の連続体といったものではない。たしかにソシュール自身もそうした誤解を招きかねない「星雲」といった比喩を使ってはいるが、あらゆるものがもつれあっているが故にそれがカオスと呼ばれるのではなく、そこにあるすべての要素がそれぞれに異なった自分をわれがちに主張しあっているが故にカオスなのである。なるほど、一見したところそこには秩序はないが、しかし、秩序はそこからしか生じえないはずのものであり、これを「コスモス=分節化されたもの」と「カオス=分節化以前のもの」の対立としてとらえるかぎり、作家としてのソシュールが視界に浮上する瞬間は訪れないだろう。「作家」とは、みずからを差異として組織することで「作品」という差異を生産するものだからである。もちろんこの差異はコスモスには属していない。
「『星雲』というのは、シーニュによる分節以前の実質である意味のマグマを指して」いると丸山圭三郎が主張している(『ソシュールを読む』、四〇頁)が、では彼は、「シーニュ」の分節能力はどこからくるというのだろうか。ソシュールにとって、「ラング」が差異の体系だといったことぐらいなら、いまでは誰もが知っている。事実、「シーニュがあるのではなく、シーニュの間の差異があるだけだ」といったたぐいのことをソシュールはいたるところで口にしているし、「シーニュ」は「純粋に否定的で示差的な価値」しか持ってはないとさえ念をおすことを忘れてはいない。だがソシュールが、そうした記号概念を知っているということは、同時に、彼自身がまぎれもなく書いた言葉の中に、あからさまにそうと明言されてはいなくとも、彼がまぎれもなく知っている別のことがらを読み取ることをうながしているはずである。
では、ソシュールはなにを知っているのか。「ラング」が差異の体系だということは、それが体系化された差異からなりたっていることを意味しているはずである。だとすれば、そう書いたものは、当然のことながら、体系化されない差異というものをも知っていることを前提としていなければなるまい。また、「シーニュが否定的で示差的な価値」を持つものだというなら、否定的ではない差異、すなわち積極的な差異というものを知っていることを前提としているはずである。事実、彼は、体系化されることのない積極的な差異なるものを明らかに知っている。「混沌たる塊」や「星雲」といった比喩で語っているものこそがそれでなければならない。そこには、体系化されることのない積極的な差異としての言語記号が無数におのれを主張しあうことで、カオスと呼ばれるにふさわしい風土を形成している。ソシュールが裸の言語記号を思考することを断念せざるをえないのは、そのひとつひとつが「イマージュ」を身にまとうことをひたすらこばみ、素肌のままであたりを闊歩するという野蛮さに徹しているからだ。これはなんとも始末におえない世界だとつぶやきながら、彼は思わず目を閉じ、耳を覆わざるをえない。
その瞬間、ソシュールの不可視の視界には、不在を告げるものとしての「イマージュ」をまとった「シーニュ」と、その体系にほかならぬ「ラング」とが、同時に音もなく浮上することになるだろう。『一般言語学講義』と『原資料』とに詳細に書き込まれているはずでありながら、「シーニュ」としてはそのように読まれることをこばんでいるのは、体系化されることのない積極的な差異の世界から体系化された否定的な差異の世界へのソシュールの余儀ない撤退ぶりにほかならない。ソシュールを読むにあって見落としてはならぬ肝心の記号は、おそらく、この差異の領域を隔てている差異をひそかに不在化してしまった「イマージュのソシュール」の身振りをめぐるものだろう。それは、差異に言及しようとするまさにその瞬間、それをすぐさま否定的なものだと定義せずにはおれず、差異の肯定を進んで放棄してしまうソシュールに対する『差異と反復』のジル・ドゥルーズの苛立ちを招いた身振りにほかならない。その身振りは、まぎれもなく記号化されているが、そのとき記号化されているものが「シーニュ」としての言語記号でないことはいうまでもない。そのことについて、「シーニュ」としての言語記号はあくまで沈黙をまもっている。
共時的現象としての言語ではなく、不等質な《動く差異》が戯れている領域としてのその通時的な側面に注目する立川健二は、あたかもソシュールが「ダイナミックで自由な<差異>の運動」を生きることをわれわれに示差しているかのごとくに語ってはいる。それは、「表象不可能な<運動>」にほかならず、ソシュールが難儀しながら何とか語ろうとしたのはこの語りえぬものなのだと彼はいうのだが、それは、体系化された否定的な差異と体系化されることのない積極的な差異との差異をソシュールが充分に意識しており、後者から前者への撤退はみせかけにすぎないという視点にほかなるまい。「イマージュのソシュール」に対して「力のソシュール」というものが存在しており、そうした可能性の中心においてこそソシュールは読まれるべきだというのだろう。
もちろん、『《力》の思想家ソシュール』を擁護するみちはそれしか残されておらず、できればわれわれからもそうすることでソシュールを救いたいとさえ思う。だが、「通時的現象によって創り出された差異」によって「共時的現象の本質」をなすというソシュールの言葉を立川はいささか楽天的に誤解しているかにみえる。それは、「アポセーム変化」といった術語を作り上げて論ずべき問題ではなく、「シーニュ」が反復されることで心的刻印として固定化され、差異が体系化されるというごく当たり前の過程を述べているにすぎず、それがないかぎり「ラング」の共時的な秩序など成立しがたいのは当然だろう。しかも、立川が語りえぬものだという《動く差異》とやらの運動に身をさらすということは、かりにそんなことが可能だったとして、ごく単純に言語についての「イマージュ」を決定的に失うことを意味しており、「ダイナミックで自由な」振舞いだの、「固定したシステム=制度」からの解放だのといった楽天性とはいっさい無縁の思考放棄につながるものである。なるほど、ソシュールは、諦念に彩られた振る舞いとして言語の「イマージュ」へと撤退しはしたが、それは、この種の楽天的な身振りだけはおのれに禁じようとする厳しさを見失わずにおくためではなかったか。
余儀ない撤退からひたすら沈黙への道を選ぶソシュールのこの不幸な肖像の成立を、言語学の意識されざる「形而上学」化という言葉で呼ぶことはいくらでも可能である。あるいはそこで、「形而上学」の伝統が「現象学」的な思考とひそかに連繋し、装いを新たにしたのだといえるのかもしれない。たとえば、二〇世紀的な「知」の支配的な形態と呼ぶこともできよう「構造主義」的な思考のかなりの部分が、撤退しつつ沈黙する「ソシュールのイマージュ」の記憶を無自覚に反芻することでかたちづくられていったことは、否定しがたい現実だからである。もっぱら「イマージュ」を介して運動する思考が、「イマージュ」を欠いた世界での体験の記憶をいささかもとどめていないという意味でなら、「ソシュールのイマージュ」の無意識の反芻によって形成される「知」の支配的な形態のことごとくを、たとえば唯物論的な身振りの回避として定義することも可能である。さらには、同じ理由によって、体系化されることのない積極的な差異にほかならぬ複数性の活動を思考から徹底的に追放しようとする風土の無自覚な定着を、近代のニヒリズムのあからさまな露呈ととらえることもできるだろう。そのことに苛立つ風情もないまま思考がかさねられてゆくかのごとき現状を目のあたりにすると、思わず「魂」という古色蒼然たる言葉が筆先からこぼれ落ちてしまう。たとえば、体系化される否定的な差異の世界に保護されたまま甘美なまどろみをむさぼっている連中は、「魂」に触れぬまま、もっぱら記号の「イマージュ」のみと戯れているとしかみえぬからである。
いま、「知」の領域でおおがかりに進行しつつあるのは、この種の唯物論の回避と連携しあるニヒリズムの露呈にほからなない。文化から政治にいたるすべての領域で、たとえば複数性とは無縁の多元論に逃れたり、「形而上学」と化した民主主義の「イマージュ」を顕揚する無自覚なニヒリズムとしてこの傾向が定着されようとしている。フェルディナン・ド・ソシュールが明らかに知っていながら、それに言及することを避けることしかできなかったふたつの差異を隔てる不在化が、いたるところで思考から記憶を奪い、その活動を鈍らせてゆく。仮にポストモダンと呼ぶものが話題になりうるとしたら、あたかもこの不在化が自然な事態だといわんばかりに思考が受け入れている記憶喪失による活動の純化をおいてはないだろう。近代化された「観念論」ともいうべきこうした風潮の中でひたすら鈍り行く思考は、二つの差異の間の差異を知っていたことの痕跡さえとどめぬ「イマージュ」の世界のみを視界に認めているが故に、かえってすべてがすがすがしく冴えわたっているかの錯覚と戯れることができる。ひろく共有されているこの錯覚に対する闘いが、複数性の擁護として闘われなけれなならないことを、ソシュールは少なくとも自覚していた。だが、それに続くものとして形成された二〇世紀の「知」の体系のほとんどは、その自覚からの余儀ない撤退を、あたかも自然なこととして容認してしまっている。
その容認を自然なものとしては容認せずにおくこと。それが、ソシュール以後に生きるものたちの思考の身振りでなければならない。「魂」の唯物論的な擁護がいささかの倒錯性も身にまとうことなくいま始まろうとしている。(蓮實重彦『「魂」の唯物論的擁護にむけて ――ソシュールの記号概念をめぐって 丸山圭三郎の記憶に』「ルプレザンタシオン」第五号所収 1993年)