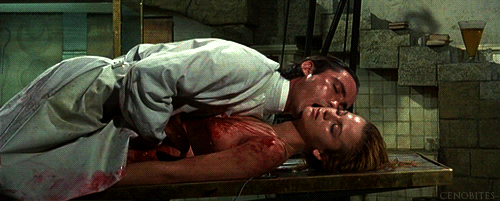幼児性愛はどうか。これにはインフォームドコンセントという壁がある。
セクシャリティとエロティシズムの問題において、現在ーー少なくとも西側先進諸国のあいだではーーほとんど何でも可能だ。これは、この20年間のあいだに倒錯のカテゴリーに含まれる症状の縮小をみればきわめて明白だ。現代の倒錯とは、結局のところ相手の同意(インフォームドコンセント)の逸脱に尽きる。この意味は、幼児性愛と性的暴力が主である、それだけが残存する倒錯形式のみではないにしろ。実際、25年前の神経症社会に比較して、現代の西洋の言説はとても許容的で、かつて禁止されたことはほとんど常識的行為となっている。避妊は信頼でき安い。最初の性行為の年齢は下がり続けている。セックスショップは裏通りから表通りへと移動した。(ポール・バーハウ Paul Verhaeghe, Sexuality in the Formation of the Subject、2005)
東インドのある地方では、思春期以前の結婚や同棲生活が、いまでも珍しくない。八十歳を越したレプチャ族の長老たちは八歳の少女と交接するが、誰もべつだん奇異とは感じないらしい。ダンテがベアトリーチェと熱烈な恋をしたとき、彼女はまだ九歳の才気あふれる少女だった。深紅の衣裳や宝石で身を飾り、薄化粧をほどこした愛らしい少女だった。これは一二七四年にフィレンツェでひらかれた楽しい五月のある内輪の宴での出来事だ。またペトラルカがロリーンに熱狂的な恋をしたとき、彼女は花粉を吹きちらす風のなかを走りまわる十二歳の金髪のニンフェットで、ヴォクルーズの連丘から眺めた姿は、さながら美しい平原に舞い踊る一輪の花だった。(ナボコフ『ロリータ』)
最近アメリカのいくつかの集団で再浮上してきたある提案(……)。その提案とは、屍姦愛好者(屍体との性交を好む者)の権利を「再考」すべきだという提案である。屍体性交の権利がどうして奪われなくてはならないのか。現在人々は、突然死したときに自分の臓器が医学的目的に使われることを許諾する。それと同じように、自分の死体が屍体愛好者に与えられるのを許諾することが許されてもいいのではないか。(ジジェク『ラカンはこう読め!』)
日本でもこの二人の作家に導かれて近親相姦・幼児性愛・屍姦愛等の擁護の動きがあることを望みたい。
ところでジジェクの「愉快な」マイノリティ擁護揶揄の文がある。
この文を想起しつつ、わたくしの偏見にみちたアタマでは、阿呆鳥作家の擁護運動をせねばならぬのではないかという危惧を捨て切れていないのである。
だがそれは杞憂とでも言うべきものだろう。経験豊かな、かつまたいくつかの作家賞を受けている二人である。わたくしが次のような悪臭を嗅いでしまったのは、たんに鼻のぐあいがわるいための錯覚である。
・マイノリティの側に立つこと、マイノリティとの同一視は、私たちの荷を軽くしてくれ、私たちのマジョリティ的側面を一時忘れさせ、私たちを正義の側に立たせてくれる。
・現在、わが国におけるほとんど唯一の国民的一致点は「マイノリティの尊重」である。
・「マイノリティの尊重」とは、表面的な、利用されやすい庶民的正義感のはけ口に終わる可能性が高い。
ああ、ニーチェほどの鼻があればよかったのに! そうであればこんなふうに「錯覚としての」悪臭や嘔吐感に悩まされずにすんだのだが・・・実に忸怩たる思いである。
ところでジジェクの「愉快な」マイノリティ擁護揶揄の文がある。
聾者の国 Deaf Nation の事例を取り上げてみよう。 今日、「耳の不自由な」人のための活動家は、耳が不自由であることは傷害ではなく、別の個性 separateness であることを見分ける徴であると主張する。そして彼らは聾者の国をつくり出そうとしつつある。彼らは医療行為を拒絶する、例えば、人工内耳や、耳の不自由な子供が話せるようにする試みを(彼らは侮蔑をこめて口話偏重主義 Oralism と呼ぶ)。そして手話こそが本来の一人前の言語であると主張する。“Deaf”に於ける大文字のDは、聾は文化であり、単に聴覚の喪失ではないという観点をシンボル化している。(Margaret MacMillan, The Uses and Abuses of History, London 2009による)
このようにして、すべてのアカデミックなアイデンティティ・ポリティクス機関が動き始めている。学者は「聾の歴史」にかんする講習を行い、書物を出版する。それが扱うのは、聾者の抑圧と口話偏重主義 Oralism の犠牲者を顕揚することだ。聾者の会議が組織され、言語療法士や補聴器メーカーは非難される、……等々。
この事例を揶揄するのは簡単である。人は数歩先に進むことを想像しさえすればよい。もし聾者の国 Deaf Nation があるなら、視覚偏重主義の圧制と闘うために、どうして盲者の国 Blind Nation が必要ないわけがあろう? 健康食品と健康管理圧力団体のテロ行為に対して、どうしてデブの国 Fat Nation が必要でないわけがあろう? アカデミックな圧力に残忍に抑圧された人たちにとって、どうして阿呆の国 Stupid Nation が必要でないわけがあろう?(ジジェク、LESS THAN NOTHING、2012 )
この文を想起しつつ、わたくしの偏見にみちたアタマでは、阿呆鳥作家の擁護運動をせねばならぬのではないかという危惧を捨て切れていないのである。
だがそれは杞憂とでも言うべきものだろう。経験豊かな、かつまたいくつかの作家賞を受けている二人である。わたくしが次のような悪臭を嗅いでしまったのは、たんに鼻のぐあいがわるいための錯覚である。
・マイノリティの側に立つこと、マイノリティとの同一視は、私たちの荷を軽くしてくれ、私たちのマジョリティ的側面を一時忘れさせ、私たちを正義の側に立たせてくれる。
・現在、わが国におけるほとんど唯一の国民的一致点は「マイノリティの尊重」である。
・「マイノリティの尊重」とは、表面的な、利用されやすい庶民的正義感のはけ口に終わる可能性が高い。
……被害者の側に立つこと、被害者との同一視は、私たちの荷を軽くしてくれ、私たちの加害者的側面を一時忘れさせ、私たちを正義の側に立たせてくれる。それは、たとえば、過去の戦争における加害者としての日本の人間であるという事実の忘却である。その他にもいろいろあるかもしれない。その昇華ということもありうる。
社会的にも、現在、わが国におけるほとんど唯一の国民的一致点は「被害者の尊重」である。これに反対するものはいない。ではなぜ、たとえば犯罪被害者が無視されてきたのか。司法からすれば、犯罪とは国家共同体に対してなされるものであり(ゼーリヒ『犯罪学』)、被害者は極言すれば、反国家的行為の単なる舞台であり、せいぜい証言者にすぎなかった。その一面性を問題にするのでなければ、表面的な、利用されやすい庶民的正義感のはけ口に終わるおそれがある。(中井久夫「トラウマとその治療経験」『徴候・外傷・記憶』所収)
ああ、ニーチェほどの鼻があればよかったのに! そうであればこんなふうに「錯覚としての」悪臭や嘔吐感に悩まされずにすんだのだが・・・実に忸怩たる思いである。
最後に、わたしの天性のもうひとつの特徴をここで暗示することを許していただけるだろうか? これがあるために、わたしは人との交際において少なからず難渋するのである。すなわち、わたしには、潔癖の本能がまったく不気味なほど鋭敏に備わっているのである。それゆえ、わたしは、どんな人と会っても、その人の魂の近辺――とでもいおうか?――もしくは、その人の魂の最奥のもの、「内臓」とでもいうべきものを、生理的に知覚しーーかぎわけるのである……わたしは、この鋭敏さを心理的触覚として、あらゆる秘密を探りあて、握ってしまう。その天性の底に、多くの汚れがひそんでいる人は少なくない。おそらく粗悪な血のせいだろうが、それが教育の上塗りによって隠れている。そういうものが、わたしには、ほとんど一度会っただけで、わかってしまうのだ。わたしの観察に誤りがないなら、わたしの潔癖性に不快の念を与えるように生れついた者たちの方でも、わたしが嘔吐感を催しそうになってがまんしていることを感づくらしい。だからとって、その連中の香りがよくなってくるわけではないのだが……(ニーチェ『この人を見よ』)