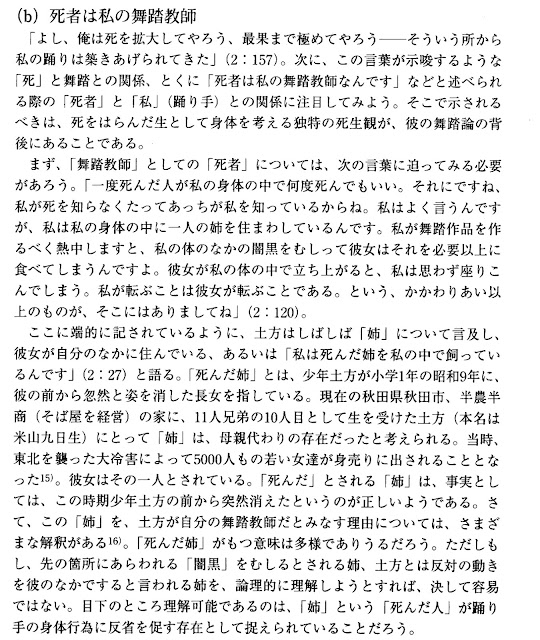|
◼️土方巽「犬の静脈に嫉妬することから」『美貌の青空』第一章より |
|
屋根からころげ落ちた時、口に碍子をくわえていた。これだけの理由で故郷を追放された男の、あの風呂敷を握った掌の事を考えると、途端に真黒こげになってしまう。 * 母親についての最初の記憶といっても、私は十一番目ですから、最初じゃないわけですよ。 しかも末子だとか末っ子だとかいうよりは、ボタボタ落して、十一番目に落されたような感じで、産声だとかいう時の声も挙げてないわけだ。産んだ次の日から水屋に立って仕事をしているような人でしたよ。 朝の三時頃起きて、ナタを持って土間に降り、甕の氷を割ってから飯の火を炊く。髪を結わえてないから、髪にボーボーと火がついたり、竈のそばに立っていると、おふくろがいっしょに燃えているんじゃないかと思いました。そういう角度から見ると、何かとてもこわい生きものが土間に降りたという感じもしましたね。 二十一貫ありまして、血圧が高くて(だから風通しをよくするために、毎日、頭のてっぺんを剃ってました)ただ囲炉裏ばたにドカッと坐って、いるのかいないのか。たまにいるのに気づくと、変な人がいるという感じでみんなが笑うわけですよ。それでいて、親しみがないわけじゃない。 |
|
ただ、私が三つの時、ジフテリアにかかったんです。夜になると、何か変な咳をする。すると、ものも言わず背中に結わえて、夜道をどんどんどんどん医者まで走るんですね。 その時背中で、「いまだ」と思う瞬間がありました。母親と子どもというようなものが、ね。しかし、「いまだ」と思ってあげるのは子どものほうで、母親はぜんぜん感じていないらしく、病院についてもハアハア息しているわけですね。 親父がこわい親父でね、子供に物を投げるんですが、 最初になぐられるのが母親でしたよ。一応、土間ヘダダダッと逃げて行くんですが、あとから追っかけて行くんですね。コンコンコンと音がしてるんです。 母親は黙って叩かれているだけです。 ある日、やはり大喧嘩が起ったんですよ。その時はボッと出たんだね。私がうんと小さい時でしたから、まだ若かったんでしょう。角巻を着て、角巻の中に四つぐらい頭を入れて歩いたんですよ。隣りの天徳寺という村まで二里以上、歩くわけです。途中で眠くなるんですが、必死になってつかまっているわけですよ。ふつうの母親ならもう少しタカをくくれるでしょうが、一人一人ちぎって投げられるんじゃないか、道ばたに置いて行かれるんじゃないかという恐怖観念があるんです。 結局、親父が来て連れ戻されましたがね。 |
|
家は半農のそば屋でしたからね。農繁期は朝から田んぼに働きに行くわけです。こどもは飯詰といってご飯を入れる藁の丸い桶の中に入れて、田んぼの畔に置くんです。 朝の七時ごろから連れて行かれて、月の出るまで放って置かれるんだ。もちろん、ご飯の時は、おふくろが来て飲みものを飲ませて行きますが、ね。 飯詰に入れられて、まわりにいろんなものが詰められて、出られないように結わえられて、子供ですからたれ流しでしょ、下半身の世界が、むずがゆくなるわけです。それで泣くんです。私だけじゃない、あっちこっちの田んぼにポンポンと置かれている。それが、ピャーッと泣くけれども、働いている人に届かないんですよ。 田んぼだから、空があまりにも広くて、それから風でしょう。だから、空見て「大馬鹿野郎だ」と思いましたよ。 夕暮れになって中から抜かれると立てないんです。 完全に足が折れて、いざりになっていますよ。子どもは絶対に家族の顔を見ない。畳まれた関節がそこに置かれている。それは滑稽で、とても厳粛です。せっぱつまっているわけです。足が鉢からスーッと逃げて行く気がする。行ったきり戻らない足はどこに行ったのか。それは子どもの飯詰にいじめぬかれた躰だけが知っているような気がします。 |
|
おふくろと親父が夫婦になったのは、見合いというものでもなかったらしい。何か橋が一本あって、あっちからとこっちからと歩いて来て、こっちで背負っちゃった、 それで連れて来たというんです。それはこういうことなんです。親父のうちというのは村長で、そこにめらしがたくさんいて、おふくろがその一人だったわけですよ。小さい時から預けられていたんだな。ロベらしですよ。それで見染めたんでしょうね。見染めたにしても、やはり結ばれるために、どこか場所がなければならないでしょう。家に帰る途中だったのか、風呂敷を持ってとっとと来たら向うから来るので、背負ってあと、そのまんまいっしょになったという話ですね。だから結婚式とか、やってないんじゃないですか。それが手つづきだったような気がします。 家にいても、いるかいないかわからないような母親でしたが、三番目の兄貴がはじめて兵隊に行く前に映画を見に連れて行ったんですよ。「雪之丞変化」という映画だったのですね。そしたら、次の日から働かなくなったんです。 「あんなにきれいな男っているもんかなア」と一言いって、水屋に立って皿洗ったりあまりしなくなった。その時、何かおこったはずなんですよ。 長谷川一夫見て、抵抗を示したのかな。おれもオナゴだとか。 |
|
* 死んだのは十年前ぐらいですかね。死ぬ時も、囲炉裏ばたで、囲炉裏にドタンと頭が落ちて死んだといいますから、あとから聞いたら、親父がおふくろのおしめを川で洗っていたといっておりましたよ。おふくろが死んで親父はずいぶんガックリいったんじゃないでしょうかね。 生きてる時は親父のほうが断然大きかったけど、この頃、母親の存在が私の中でだんだん大きくなって来ました。要するに、欲がないですからね。愛だけでしょう。 欲があると欲のほうで愛を食っちゃうから。よく「親がなくても子は育つ」なんていうけれども、一面の真理ですね。 私は、私の体のなかにひとりの姉を住まわせている。私が舞踊作品を作るべく熱中するとき、私の体のなかの闇黒をむしって、彼女はそれを必要以上に食べてしまうのだ。彼女が私の体の中で立ち上ると、私は思わず坐りこんでしまう。私が転ぶことは彼女が転ぶことである。というかかわりあい以上のものが、そこにはある。* |
|
* 五体満足でありながら、しかも、不具者でありたい、いっそのこと俺は不具者に生まれついていた方が良かったのだ、という願いを持つようになりますと、ようやく舞踏の第一歩が始まります。びっこになりたいという願望が子供の領域にあるように、舞踏する人の体験の中にもそうした願望が切実なものとしてあります。 びっこの犬が人眼を避けて逃げるのを、子供が石や棒で追跡して、壁板のあたりに追いつめて、やたらに叩きのめしているのを見ますと、わたくしはある種の嫉妬を犬に感じます。 なぜなら、得をしているのは犬の方だからです。犬が人の子を誘惑して、場所柄もわきまえず、あらん限りの姿態をさらしているからです。ある種の犬は腹の中から赤い腸などを垂らして、それをやっているのです。〔・・・〕 犬に打ち負かされる人間の裸体を、私は見ることができます。これはやはり、舞踏の必須課目で、舞踏家は一体何の先祖なのかということに、それはつながってゆきます。 わたくしはあばらの骨が大好きですが、それも犬の方が、わたくしのそれよりも勝っているように思われます。これも古い心象なのでしょうか。雨の降る日など、犬のあばらを見て敗北感を味わってしまうことがあります。それにわたくしの舞踏には、もともと邪魔な脂肪と曲線の過剰は必要ではないのです。骨と皮、それにぎりぎりの必要量の筋肉が理想です。 |
…………………
|
《この一篇は土方巽の求めに応えて書いたものである。》(吉岡実「土方巽頌」) |
|
青い柱はどこにあるか? |
|
闇夜が好き 母が好き つとに死んだカンガルーの 吊り袋のなかをのぞけ テル・テルの子供 ニッポンの死装束が白ならばなおさら 青い柱を負って歩き給え 円の四分の一の スイカのある世界まで 駈け足で ときには バラ色の海綿体へ 沈みつつ 犬の四つ足で踊ること かがまること 凍ること |
|
天井の便器のはるか下で ハンス・ベルメールの人形を抱き 骨になること それが闇夜が好きなぼくたちの 暁の半分死 ある海を行き ある陸を行き ラッパのなかの井桁を吹き むらさき野を行き ふたたび闇夜を行く 美しき猫の分娩 そのしている夢 そのうえしてない行為 |
|
ぼくたちはどうしている? すべてに同化する 末梢循環の恥毛性存在! 消えなん横雲の空 鋼鉄のビル・ビルの春 ビー玉の都市 そこにサクラは散るや 散らずや 赤い映像とは肉体の終り ガニ股の父が好き 心中した姉が好き 古典的な死の隈取 闇夜が好き かがり火が見えるから 大群衆が踊り狂っているんだ 亜硫酸ガス 濃霧 予定のない予定? |
|
黄いろの矢印に沿って 柱に沿って 形而上的な肛門を見せ ひとりの男が跳ねあがる 一九六七・五・一五 |
|
聖あんま断腸詩篇 〈神の光を臨終している〉 土方巽 Ⅰ 物質の悲鳴 「この狂おしい 美貌の青空」 軍鶏の首をつかんでいる 「あの老婆も狼煙の一種で あったかもしれない」 私は生きている者 そして一度は通って みたいような(処)へ差しかかる |
|
「物質の悲鳴が聞こえた」 小鳥の声も聞こえるなかで 「言葉が堕胎されている!」 散乱するもの 肉片 破片 記号 「人間的な言語が多量すぎる」 ゴムの鳩を抱いて 少女が立っている この異常な明るさは 「光じゃありませんよ もう闇ですよ」 ここは(仮の地)? オガクズが敷かれていた 「灰柱まで 私の死への歩行が続いている」 |
|
Ⅳ 故園追憶 私は(骸骨)で生まれたのだ/弥生の曇った空の下で/こ の秘密は父母しか知らない/ああ(骨の涼しさ)/湯気の ような(肉体)を着せられて/初めて産声をあげる/みど りごに成り/ブリキの匙で片栗粉を口に流しこまれる/甘 露!/だから途中から肉が付き/梨頭の子供へ変る/ほん とうに冷えた砂枕が好き/夏のひるさがり/姉とは突然に (家)からいなくなるものだ/ 鳶が風を切って降りて来る /草深い外の面の沼で/沈んでいる亀/畷を歩きながら死 んでいる人たち/風のさわぐ日に限って/鹿肉を売る商人 が来る/父親はそれを(神品)として大事にする/蕗の葉 や芋の葉の上に/ころがる滴玉/また道端で転んでいる老 人が多かった/私は板のささくれた面に/クレヨンで/兎 の絵を描く/ついでに(女陰)も/今朝早く水田から上っ てくる/女を見た/私は美しい少年へと/身の丈が伸びる /なまなましい蛇の抜け殻/ |
|
裏庭の七面鳥がホロホロと鳴 く/引き抜かれた/草のように衰弱している人の声/棚の 上から招き猫が転がり/暗い畳表へとんであがる雀/天狗 の面やおかめの面が掛けられた/粗い壁/濡れた笊/寝床 に入ると/眼をつむって/柿など啜っている/花嫁姿の人 を想う/この頃は(夢の沈澱物のような私)/ 太い醤油瓶 の間に/張られた蜘蛛の巣が破れた/埃と手拭のにおいの する/母親の肩にさわる/板の間に置かれた/茗荷は淋し い/ニガリの効いた(時空)/どんどん色の変ってゆく/ 鯖を洗っている兄/古い糊のような/臭いのする/掛け軸 の龍/ 肥桶の周りを/恐るおそる駈け廻る/聖なる赤い着 物の日本の少女たち/樟脳の香気/霞んでゆき/人さらい の懐は深く/空気で出来ているように/感じられた/村の 晩秋/雨は鮒の(精霊)に降り注ぐ/ |
|
私はいまでは(精神) の洟をたらしている/人体の冬/燠炭のような病気の男が /足もとの柄杓で水をかけている/(物質)か(言語)/ 見よ/馬が風雪に晒されている光景/蹄鉄の火花から/ (人間)は火種を貰って来る/私は一生カルメラを焼いて /暮したいと思ったり/この寒夜を/家のなかで沸騰する 薬缶が在る/塩鱈が出刃庖丁で切られている/(時間)/ 永遠に終らないもの―― |
|
Ⅶ 像と石文 「言葉から肉体が発生する」 この認識をみとめよ 雨傘をさしたまま (無体)と化しつつある (泥型立身像) このささくれた(幻像)を記憶せよ それを冒す 「血と霊と風と虫とが交合する」 森を抜けるんだ 「書く者は衰弱し 死者にかぎりなく近付く」 そのように刻まれた(石文) 現われたり 消えたり 「大暴風雨にさらされている 鹿のようなものが見えた」 |
|
Ⅷ 慈悲心鳥 菊の束で大地を叩いている者 (亡霊)ではなく (誰?) 「骨まで染めるような 夕焼」 比喩的に言えば (魂と炎の世界) |
|
初出《新潮》(新潮社)1986年6月号 |
|
注 この作品は、おもに土方巽の言葉の引用で構成されている。また彼の友人たちの言葉も若干、補助的に使わせて貰っている。なお冒頭のエピグラムは、彼の辞世である。 |