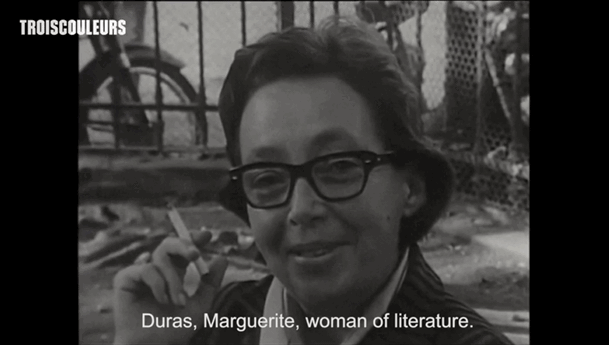|
| Godard、HISTOIRE(S) DU CINEMA、1A |
「映画とは女と銃なり」と《言ったのは、グリフィスであり、私ではない c'est Griffith qui a dit ça, ce n'est pas moi 》(ゴダール)
そして御覧の通り、銃は銃それ自身である以上に、撮影機である。
きみたちの国でも、荒木経惟くんが言っているではないか?「男と女の間には写真機がある」と。
私がとった風景写真には、ふしぎな特徴があると友人はいう。要するにみごとに人がいないのである。私は意識していないのだが、かなりの雑踏でも人の途絶える瞬間があって、その時をねらってシャッターを押すらしい。(……)
写真をとるということは、機関銃に似た固い物体を相手にむけるという行為である。写真をとることにも、とられることにも、私に抵抗があるのは、このためもあるらしい。つまり、私の心の中にある対人恐怖に、相手から攻撃されること、人を攻撃してしまうことの恐怖が加わって、写真というものを苦手にしているらしい。
カメラを介しての人間関係には独特なものがある。肖像画を描いてもらう時とはずいぶん違うだろう。冷たい機械を間にはさんで直接向き合う対人場面は他にはめったにあるまい。しかも、ここには絶対的な不平等がある。写す者と写される者との不平等である。さらに、集団写真といっても、焦点は誰かに合っている。基本的には一対一の関係、それも焦点をしぼった鋭い関係である。そして、非言語的関係である。沈黙が強要され、しぐささえも一瞬の静止を求められ、自己身体のイメージが前面に出る。写真機の前で緊張する人は、この独特な状態に自分の病理をしぼり出される。私など、その最たるものであろう。(中井久夫「顔写真のこと」『記憶の肖像』所収)
もっとも肝腎なのは、カメラと銃の関係に自覚的であることだ。
 |
| Robert Mapplethorpe |
……われわれの興味を惹くのは、彼(マクシム・デュ・カン)の写真への関心が、狩猟の快楽を知ったのとほぼ同じ時期に芽萌えているということだ。彼は動物めがけて銃弾を撃つように、廃墟や歴史的建造物にレンズを向けているのである。(……)
撃つことにも通ずる撮ることという主題は、写真技術の飛躍的な進歩を達成した二十世紀に入ってから神話化されることになろうが、その原初的なかたちが無意識ながらマクシムによって実践されている点に注目しようではないか。遥かな距離にある対象物に照準を合わせること、そして指の微妙な動きが成功と失敗とを分けへだてるという物理的な類似にとどまらず、ある攻撃的な衝動なしには達成されがたい振舞いとして、撃つことと撮ることとの心理的な類縁性が、すでに写真の発生期に、狩猟の快楽に目覚めたばかりの旅行家によって実践されている点に、われわれは改めて興味をおぼえる。ある種の征服欲の発現なしには、撃つことも撮ることも真の目的を遂げえないだろう。(蓮實重彦『凡庸な芸術家の肖像』)
もちろん現代の写真家や映像作家には、カメラの銃としての機能に居直って撮るタイプとそれに抵抗して作品を撮るタイプがあるだろう。
ゴダールの『(複数の)映画史』には、マグリット・デュラスの顔が何度も大写しで現れる。あれは、作家としてだけではなく、映像作家としてのデュラスに敬意を払っている仕草である。デュラスの映像作品を眺めてみると「後ろ姿」の作家という印象を抱く。
あるいは映像作家としても《外部の物音にじっと耳を澄ましている状態》の「穴」の人である。
書くときに私が到達しようと努めているのは、おそらくその状態ね。外部の物音にじっと耳を澄ましている状態。ものを書く人たちはこんなふうに言う、 "書いているときは、集中しているものだ" って。私ならこう言うわ、 "そうではない、私は書いているとき、完全に放心しているような気がする、もう全く自分を抑えようとはしない、私自身、穴だらけになる、私の頭には穴があいている" と。(デュラス/ポルト『マルグリット・デュラスの場所』)
彼女が映像を使ってやろうとしたのは、銃としてのファルスから逃れる試みでなくてなんだろう?
ゴダールの伴侶、アンヌ=マリー・ ミエヴィル Anne-Marie Mièvilleにも銃としてのカメラから逃れるようとする試みがあるとわたくしは感じるが、彼女はどこかで「被写体はカメラを向けると変貌してしまう」という意味合いのことを言っていた記憶があるが、はてどこでそういっていたのかは今は想い起せない(参照:逆光を浴びて祈る少女)。