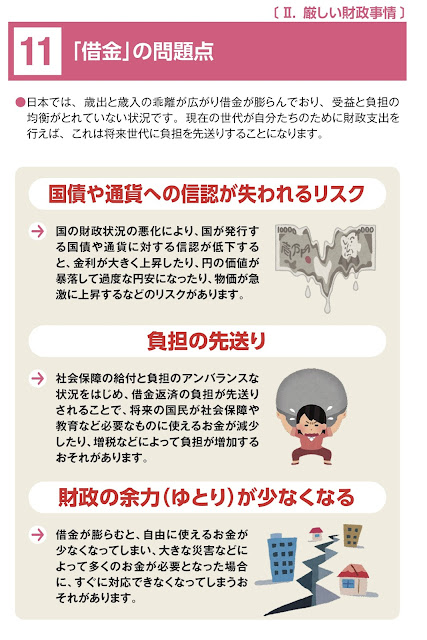10年前には次のような図がしばしば提示された。
社会保障制度が始まった時には、高齢者1人当たり生産年齢人口は11人いた。だが2014年には2.4人しかいなくなった。つまり生産年齢人口が高齢者を支える負担は5倍近くになったということだ。これが池尾和人が《政治の仕事は、むしろ負担を配分することに変わってきている》が言っていることの内実だ。
◼️経済再生の鍵は不確実性の解消 (池尾和人&大崎貞和) |
大崎:今のお話を伺っていて思ったのは、政策当事者が事態を直視するのを怖がっているのではないか、ということです。例えば、二大政党制といっても、イギリスやアメリカでは、高福祉だけれども高負担の国をつくるという意見と、福祉の範囲を限定するけれどもできるだけ低負担でやるというパッケージの選択肢を示し合っているように思います。 日本ではどの政党も基本的に、高福祉でできるだけ増税はしない、どちらかというと減税する、という話ばかりです。実現可能性のあるパッケージを示すことから、政策当事者が逃げている気がします。 |
池尾:細川政権が誕生したのが今から18年前です。それ以後の日本の政治は、非常に不幸なプロセスをたどってきたと感じています。 それ以前は、経済成長の時期でしたので、政治の役割は余剰を配分することでした。ところが、90年代に入って、日本経済が成熟の度合いを強めて、人口動態的にも老いてきた中で、政治の仕事は、むしろ負担を配分することに変わってきているはずなんです。余剰を配分する仕事でも、いろいろ利害が対立して大変なんですが、それ以上に負担を配分する仕事は大変です。 大崎:大変つらい仕事ですね。 |
池尾:そういうつらい仕事に立ち向かおうとした人もいたかもしれませんし、そういう人たちを積極的にもり立ててこなかった選挙民であるわれわれ国民の責任も、もちろんあると思います。少なくとも議会制民主主義で政治家を選ぶ権利を与えられている国においては、簡単に「政治家が悪い」という批判は責任ある態度だとは思いません。 しかしながら事実問題として、政治がそういった役割から逃げている状態が続いたことが財政赤字の累積となっています。負担の配分をしようとする時、今生きている人たちの間でしようとしても、いろいろ文句が出て調整できないので、まだ生まれていない、だから文句も言えない将来世代に負担を押しつけることをやってきたわけです。〔・・・〕 |
デフレから脱却しなければいけないのだけれども、そのプロセスについてはかなり慎重に考えなければいけません。 インフレになれば債務者が得をして債権者が損をするという感覚があります。しかしそれは、例えば年収と住宅ローンのように、所得1に対して抱えている負債がせいぜい2、3ぐらいのときの話です。 日本の置かれている状況は、一般会計の税収40兆円ぐらいに対し、グロスで1,000兆円ぐらいの政府債務があるわけです。そうすると、1対25です。景気がよくなって税収が増えたとしても、利払いの増加のほうがその上をいく構造になっています。ですから、景気が好転するときが一番用心すべきときになります。 |
あるいは武藤敏郎がより具体的に言っていることだ。
|
これまでの社会保障政策を長期的に振り返ると、引退世代の人数が増える分以上に現役世代の負担率を上昇させながら、引退世代の生活水準を向上させてきた。引退後の生活に余裕と潤いがあるのは素晴らしいことだが、「超」がつく少子高齢化の下では、現役世代 1 人当たりで支えなければならない引退世代の人数が急速に増えるから、引退世代の生活水準を維持するだけでも現役世代の負担が大きく増えていく。そうなれば、これまでのように引退世代の生活水準を向上させることは難しくなる。 〔・・・〕 |
|
日本の財政は、世界一の超高齢社会の運営をしていくにあたり、極めて低い国民負担率と潤沢な引退層向け社会保障給付という点で最大の問題を抱えてしまっている。つまり、困窮した現役層への移転支出や将来への投資ではなく、引退層への資金移転のために財政赤字が大きいという特徴を有している。引退世代向けに偏重した社会保障制度をもっと効率化し、一定の負担増を求める必要性は、経常収支が赤字か黒字かとは関係がない。 (大和総研「超高齢日本の 30 年展望 持続可能な社会保障システムを目指し挑戦する日本―未来への責任 」理事長 武藤敏郎 監修 、2013 年5 月 14 日) |
重要なのは、まず現在の財政について政治家が話しているとき、この観点をしっかり視野に入れて語っているか否かだ。
私は、切りのいいところで、1990年と2020年を比較した図を何度か掲げているがね。
1990年に比べてさえ、2020年は高齢者を支えるために生産年齢人口は3倍近く負担しなくてはならない。そんなことは不可能だから国は赤字国債を発行して穴埋めしている。
国債の金利が低かった時代は、国債残高が雪だるま式に増えてもなんとかなった。だが現在はまったく違う。
 |
| (財政を考える、財務省 令和7年4月、PDF) |
減税ポピュリズムとは、この観点を見ないふりしたままの主張だ。これは最低限の前提にすぎないが、まずはこの前提をしっかり念頭に入れて意見を述べることだよ。これが前投稿「減税ファシズムをなんとかしろよ」で記したことの基盤だ。
この今も異常事態が起こっている。
実際、「減税ファシズム」は日本の支配的イデオロギーになりつつある。もはやインフレ税過熱しか道はないのかもしれない。
ザイム真理教やら財務省カルトやらと世迷言をいまだもって言っている政治家や評論家たちがいるのを知らないわけではないが、ま、私に言わせれば彼らを信じる者たちこそ世迷言カルトだ。
世迷言カルトたちはまず消費税減税を言う。
消費税廃止一択を真顔でノタマウ政治家さえいる。
だが清滝信宏プリンストン大教授ーー現在の日本人のなかでノーベル経済学賞に最も近いところにいるとされるーーが懇切丁寧に説いているように、所得税でもなく法人税でもなく、また社会保険料でもなく、税のなかでは《消費税が一番》だと強調している、 ▶︎「消費税はその種のものとしては最高さ」。《ゆがみがないわけではないけれども、他よりも少ない。それから課税ベースが大きい》と。これは清滝氏だけでなく、主流経済学者において「常識」である。
原口一博は実際、実に気の毒な人間である。
彼が経済音痴なのはやむ得ない。だが上の主張は、世界の消費税率と比較することさえ知らない蛸壺日本人の典型例としか言いようがない。他国はなぜ彼曰くの悪税消費税を導入し、それも多くの国で日本より高率なのか、これは最低限の問いとしてある筈である。
より詳しくはーー、
消費税など(消費課税)に関する資料 | |
所得税など(個人所得課税)に関する資料 | |
法人税など(法人課税)に関する資料 | |
国民負担率に関する資料 |
……………
なおインフレ税は深尾光洋が「日本の財政赤字の維持可能性」にて、「インフレタックス」として語っているのを少し前掲げた。 ここでは一般にもいっそうわかりやすいように加谷珪一の説明を掲げておく。 |
インフレ課税というのは、インフレを進める(あるいは放置する)ことによって実質的な債務残高を減らし、あたかも税金を課したかのように債務を処理する施策のことを指す。具体的には以下のようなメカニズムである。 例えばここに1000万円の借金があると仮定する。年収が500万円程度の人にとって1000万円の債務は重い。しかし数年後に物価が4倍になると、給料もそれに伴って2000万円に上昇する(支出も同じように増えるので生活水準は変わらない)。しかし借金の額は、最初に決まった1000万円のままで固定されている。年収が2000万円の人にとって1000万円の借金はそれほど大きな負担ではなく、物価が上がってしまえば、実質的に借金の負担が減ってしまうのだ。 この場合、誰が損をしているのかというと、お金を貸した人である。物価が4倍に上がってしまうと、実質的に貸し付けたお金の価値は4分の1になってしまう。これを政府の借金に応用したのがインフレ課税である。 現在、日本政府は1000兆円ほどの借金を抱えているが、もし物価が2倍になれば、実質的な借金は半額の500兆円になる。この場合には、預金をしている国民が大損しているわけだが、これは国民の預金から課税して借金の穴埋めをしたことと同じになる。実際に税金を取ることなく、課税したことと同じ効果が得られるので、インフレ課税と呼ばれている。(加谷珪一「戦後、焼野原の日本はこうして財政を立て直した 途方もない金額の負債を清算した2つの方法」2016.8.15) |