《私は、私という語を口にするたびに想像的なもののうちにいることになる。》(ロラン・バルト『声の肌理』)
じっさい、私がもっとも自分の弱みをさらけ出す羽目になるのは、自分の《私的なこと》を口外するときである。弱みと言っても、「スキャンダル」の危険によって、というわけではなく、むしろ、私的なことをしゃべりながら私は自分という想像物をそのもっとも堅い固形で提示してしまうからなのだ。そして想像物とはすなわち他人の捕獲権の支配下にある姿のことである。(『彼自身によるロラン・バルト』)
夏の宵、なかなか日が暮れないとき、母親たちは小道を散歩していた。子どもがそのまわりでじゃれていて、まさに祭りだった。(『彼自身』)
…………
あの青い空の波の音が聞こえるあたりに
何かとんでもないおとし物を
僕はしてきてしまったらしい
ーー「かなしみ」(『二十億光年の孤独』1952)
◆「私」 谷川俊太郎
四十余年前、主に「僕」という一人称を使って私は詩を書き始めました。ふだんも私は僕と言っていて、友人同士のあいだではときに俺になることもあったにしろ、それはごく自然な選択だったと思います。作品における一人称と現実の私とのあいだに、ほとんど距離はなかったと見ていいでしょう。第二詩集である「六十二のソネット」では一人称は「私」に統一されています。どうして「僕」を「私」に変えたのか、はっきりした記憶はありませんが、もしかすると一種の背伸びだったのかもしれない。本来はなかったであろう「僕」のニュアンス、いささか子どもっぽい、ときにはカマトトともとられかねない感じが一九五〇年代にはもうあって、それを避けたかったのでしょう。
しかし心がすべてを迎えてなおも満たぬ時
私は知られぬことを畏れ―
ふとおびえた
失われた声の後にどんな言葉があるだろう
かなしみの先にどんな心が
生きることと死ぬことの間にどんなが
私は神―と呟きかけてそれをやめた
常に私が喋らねばならぬ
私について世界について
無知なるものと知りながら
もはや声なくもはや言葉なく
呟きも歌もしわぶきもなく しかし
私が―すべてを喋らねばならぬ
それ以後の作では「僕」「私」「俺」などが混在しています。作品の中に作者、すなわち私自身ではない主人公が登場し始めたということもありますが、その主人公が直接話法で語らない場合にも、詩を書いている私と、詩の中の私とのあいだに一篇一篇の作によって異なるにしろ微妙な距離がでてきたことがその理由でしょう。つまり詩を一種のフィクションとして書くことを、私は知らず知らずのうちに覚えたと言えます。しかしこのことはこういう単純な説明では解明できない、詩というものの本質にかかわっています。私はいまだに一貫した一人称を用いることが出来ず、一篇の作を書き始めるごとに、どんな一人称にしようか迷うことが多いのです。
僕は四月に女と別れられなかつた
ーー「二つの四月」『絵本』1956)
裏返せ
裏返してくれ 俺を
俺の中の言葉たちを
喋らしてやってくれ 早く
俺の中の弦楽四重奏を
鳴らしちゃってくれ
俺の中の年取った鳥たちを
飛ばしちゃってくれ
俺の中の愛を
すっちゃってくれ 悪い賭場で
裏返せ裏返してくれ俺を
俺の中のうその真珠はくれてやるから
裏返してくれ裏返してくれ俺を
俺の沈黙だけそっとしといて
行かせてくれ俺を
俺の外へ
あの樹陰へ
あの女の上へ
あの砂の中へ
裏返せ
裏返してくれ 俺を
俺の中の言葉たちを
喋らしてやってくれ 早く
俺の中の弦楽四重奏を
鳴らしちゃってくれ
俺の中の年取った鳥たちを
飛ばしちゃってくれ
俺の中の愛を
すっちゃってくれ 悪い賭場で
裏返せ裏返してくれ俺を
俺の中のうその真珠はくれてやるから
裏返してくれ裏返してくれ俺を
俺の沈黙だけそっとしといて
行かせてくれ俺を
俺の外へ
あの樹陰へ
あの女の上へ
あの砂の中へ
飲んでるんだろうね今夜もどこかで
氷がグラスにあたる音が聞える
きみはよく喋り時にふっと黙りこむんだろ
ぼくらの苦しみのわけはひとつなのに
それをまぎらわす方法は別々だな
きみは女房をなぐるかい?
ーー「武満徹に」(『夜中に台所でぼくはきみに話しかけたかった』1965)
そんなに笑いながら喋らないでほしいなと僕は思う
こいつは若いころはこんなに笑わなかった
たまに笑ってくれると嬉しかったもんだ
おまえは今いったいどこにいるつもりなんだい
人と人のつくる網目にすっぽりとはまりこんで
いい仕立てのスーツで輪郭もくっきり
昔おまえはもっと滲んでいたよ
雨降りの午後なんかぼうっとかすんでいた
分からないことがいっぱいあるってことがよく分かった
今おまえは応えてばかりいる
取り囲む人々への善意に満ちて
少しばかり傲慢に笑いながら
おまえはいつの間にか愛想のいい本になった
みんな我勝ちにおまえを読もうとする
でもそこには精密な言葉しかないんだ
青空にも夜の闇にも愛にも犯されず
いつか無数の管で医療機械につながれて
おまえはこの文明の輝かしい部分品のひとつとなるだろう
ーー「もっと滲んで」『世間知ラズ』1993)
六十年生きてきた間にずいぶんピアノを聴いた
古風な折り畳み式の燭台のついた母のピアノが最初だった
浴衣を着て夏の夜 母はモーツァルトを弾いた
ケッヘル四八五番のロンドニ長調
子どもが笑いながら自分の影法師を追っかけているような旋律
ぼくの幸せの原型
(……)
半世紀以上昔のあの夏
※
五分前に言ったことを忘れて同じことを何度でも繰り返す
それがすべての始まりだった
何十個も鍋を焦がしながらまだ台所をうろうろし
到来物のクッキーの缶を抱えて納戸の隅に鼠のように隠れ
呑んべだった母は盗み酒の果てにオーデコロンまで飲んだ
時折思い出したように薄汚れたガウン姿でピアノの前に坐り
猥褻なアルペジオの夕立を降らせた
あれもまた音楽だったのか
その後口もきけず物も食べられず管につながれて
病院のベッドに横たわるだけになった母を父は毎日欠かさず見舞った
「帰ろうとすると悲しそうな顔をするんだ」
CTスキャンでは脳は萎縮して三歳児に等しいということだった
四年七ケ月病院にいて母は死んだ
病室の母を撮ったビデオを久しぶりに見ると
繰り返されるズームの度に母の寝顔は明るくなり暗くなり
ぼくにはどんな表情も見わけることができない
うしろでモーツァルトのロンドイ短調ケッヘル五一一番が鳴っている
まるで人間ではない誰かが気まぐれに弾いているかのうようだ
うつろいやすい人間の感情を超えて
それが何かを告げようとしているのは確かだが
その何かはいつまでも隠されたままだろう
ぼくらの死のむこうに
ーー「二つのロンド」『モーツァルトを聴く人』1994)
…………
《「私」がもはや「自身」でない以上、私が「私自身」について語ってはいけない理由はないではないか。》(『彼自身によるロラン・バルト』)
ーーこの文は邦訳ではややわかりにくい形で訳されているが、英訳では次の通り(仏原文はネット上でざっと探してみたかぎりでは行き当たらないので、当面、英訳をかかげておくーー《why should I not speak of " myself " since this " my" is no longer "the self " ?》)
ロラン・バルトの一人称単数代名詞使いの極度の繊細さをめぐっては、たとえば次の最晩年の文にも現われる。
「精神分析」とあるが、フロイトの《 私は自分の家の主人ではない(dass das Ich kein Herr sei in seinem eigenen Haus)》がまずはベースとなっている。
これについてはラカンの「愉快な」説明がある。
ラカンは、言表内容の主体 sujet de l'énoncé と言表行為の主体 sujet de l'enonciation が一致している思い込んでいる人々のことを「私は私自身の主人maîtreである」という妄想的(パラノイア的)信念の言説--《m'être à moi même》(Lacan,S.17)ーーの主体としている。
近作「世間知ラズ」と「モーツァルトを聴く人」では「ぼく」が使われていて、それは当時の私の気分による、意識的な選択でした。「私」に比べると「ぼく」は一種の傷つきやすさがあり、その頼りなさが私には必要だった。その「ぼく」は「二十億光年の孤独」の中の「僕」とは違うと私は考えています。
そんなに笑いながら喋らないでほしいなと僕は思う
こいつは若いころはこんなに笑わなかった
たまに笑ってくれると嬉しかったもんだ
おまえは今いったいどこにいるつもりなんだい
人と人のつくる網目にすっぽりとはまりこんで
いい仕立てのスーツで輪郭もくっきり
昔おまえはもっと滲んでいたよ
雨降りの午後なんかぼうっとかすんでいた
分からないことがいっぱいあるってことがよく分かった
今おまえは応えてばかりいる
取り囲む人々への善意に満ちて
少しばかり傲慢に笑いながら
おまえはいつの間にか愛想のいい本になった
みんな我勝ちにおまえを読もうとする
でもそこには精密な言葉しかないんだ
青空にも夜の闇にも愛にも犯されず
いつか無数の管で医療機械につながれて
おまえはこの文明の輝かしい部分品のひとつとなるだろう
ーー「もっと滲んで」『世間知ラズ』1993)
 |
| (私を魅惑する、背景の、女中 Me fascine, au fond, la bonne.) |
六十年生きてきた間にずいぶんピアノを聴いた
古風な折り畳み式の燭台のついた母のピアノが最初だった
浴衣を着て夏の夜 母はモーツァルトを弾いた
ケッヘル四八五番のロンドニ長調
子どもが笑いながら自分の影法師を追っかけているような旋律
ぼくの幸せの原型
(……)
半世紀以上昔のあの夏
父がもう母に不実だったことを幼いぼくは知らなかった。
※
五分前に言ったことを忘れて同じことを何度でも繰り返す
それがすべての始まりだった
何十個も鍋を焦がしながらまだ台所をうろうろし
到来物のクッキーの缶を抱えて納戸の隅に鼠のように隠れ
呑んべだった母は盗み酒の果てにオーデコロンまで飲んだ
時折思い出したように薄汚れたガウン姿でピアノの前に坐り
猥褻なアルペジオの夕立を降らせた
あれもまた音楽だったのか
その後口もきけず物も食べられず管につながれて
病院のベッドに横たわるだけになった母を父は毎日欠かさず見舞った
「帰ろうとすると悲しそうな顔をするんだ」
CTスキャンでは脳は萎縮して三歳児に等しいということだった
四年七ケ月病院にいて母は死んだ
病室の母を撮ったビデオを久しぶりに見ると
繰り返されるズームの度に母の寝顔は明るくなり暗くなり
ぼくにはどんな表情も見わけることができない
うしろでモーツァルトのロンドイ短調ケッヘル五一一番が鳴っている
まるで人間ではない誰かが気まぐれに弾いているかのうようだ
うつろいやすい人間の感情を超えて
それが何かを告げようとしているのは確かだが
その何かはいつまでも隠されたままだろう
ぼくらの死のむこうに
ーー「二つのロンド」『モーツァルトを聴く人』1994)
旅先の殺風景な狭いホテルの一室で朝、イヤフォンでモーツアルトを聴いている。曲は選べないが、このAbacus.fmのMozart Pianoというサイトはここのところ、ずっと内田光子の演奏を流している。グレン・グールドのモーツアルトも好きだが、内田光子を聴いたらグールドが野暮ったく思えてきた。美には冷静で強い透明な意志が必要だと思わせる演奏だ。(俊) 谷川俊太郎.com
ぼくの母はピアノが上手だった
小学生のぼくにピアノを教えるときの母はこわかった
呆けてから毎晩のようにぼくに手紙を書いた
どの手紙にもあなたのお父さんは冷たい人だと書いてあった
お父さんのようにはならないで下さいお願いだから
五年前に母は死に去年父も死んだ
ーー「ザルツブルグ散歩」(『モーツァルトを聴く人』1994)
小学生のぼくにピアノを教えるときの母はこわかった
呆けてから毎晩のようにぼくに手紙を書いた
どの手紙にもあなたのお父さんは冷たい人だと書いてあった
お父さんのようにはならないで下さいお願いだから
五年前に母は死に去年父も死んだ
ーー「ザルツブルグ散歩」(『モーツァルトを聴く人』1994)
一篇の詩とその作者である詩人との関係は、ふつう考えられているよりはるかに複雑微妙で流動的です。一篇の詩はたしかにその作者の現実生活なしでは生まれてこないものですが、その詩に述べられた考えや感情が、そのまま作者である詩人が現実に抱いたものであるかと言えば、そうは言えないことも多いのです。詩は思想を伝える道具ではないし、意見を述べる場でもない、またそれはいわゆる自己表現のための手段でもないのです。詩において言葉は「物」にならなければならないとはよく言われることですが、もしそうであるとすれば、たとえば一個の美しい細工の小箱を前にするときと同じような態度が、読者には必要とされるのではないでしょうか。そこでは言葉は木材のような材質としてとらえられ、それを削り、磨き、美しく組み合わせる技術が詩人に求められる倫理ともいうべきものであり、そこに確固として存在している事実こそが、詩の文体の強さであるはずです。作者である詩人は「形」の中にひそんでいる。何かを言いたいから書いたのだという視点からだけでは、詩の中の「私」はとらえられないと思いますし、詩に書かれている内容をもとにして、詩人の正邪を断罪するのも公平でないと思う。とは言うものの、詩が散文による書き物と違って、この世の道徳的判断からまったく免責されているというふうには私も考えていません。詩人はたぶん現実世界から見れば不道徳な存在とならざるをえない一面をもっていて、その自覚なしには彼ないし彼女はこの世に生きてはいけないのです。自らのいかがわしさを通して、詩人は世間にむすびつくと今の私は考えています。(谷川俊太郎「私」)
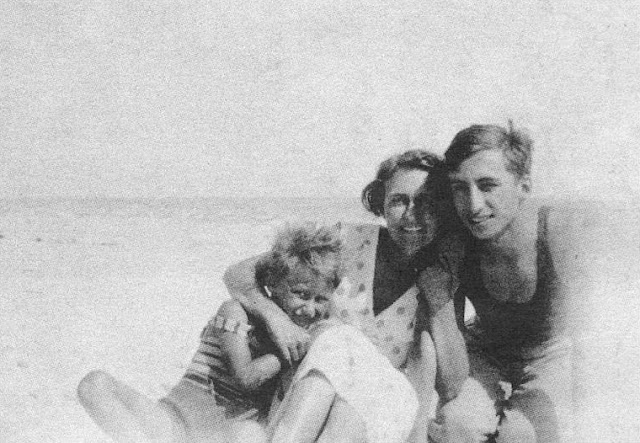 |
| (家族主義なしの家族) |
手紙で借りる話をまとめておいた家具つきのアパルトマンが、ふさがっていた。彼らは、パリのある十一月の朝、ド・ラ・グラシエール街で、トランクと手荷物をかかえて途方に暮れる羽目となった。近所の乳製品のおかみさんが、うちへ入れて、あついショコラとクロワッサンをご馳走してくれた。(『彼自身によるロラン・バルト』)
…………
《「私」がもはや「自身」でない以上、私が「私自身」について語ってはいけない理由はないではないか。》(『彼自身によるロラン・バルト』)
ーーこの文は邦訳ではややわかりにくい形で訳されているが、英訳では次の通り(仏原文はネット上でざっと探してみたかぎりでは行き当たらないので、当面、英訳をかかげておくーー《why should I not speak of " myself " since this " my" is no longer "the self " ?》)
私にとって家族は、ずっと前から、母と、血を分けた一人の弟だけだった。後にも先にもそれだけである(ただ、祖父母の思い出だけは別であるが)。家族集団を構成するためにどうしても必要とされる単位、《いとこ》は一人もいなかった。それに、家族というものを、もっぱら拘束と儀式だけで成り立っているかのように扱う、あの科学的態度は、どうにも我慢がならなかった。つまり家族は、直接的な帰属集団としてコード化されるか、または、葛藤と抑圧の結節点と見なされるのだ。われわれの学者たちには、《互いに愛し合う》家族もいるということが想像できないかのようである。
そしてまた私は、私の家族を「家族」一般に還元することを欲しないのと同じく、私の母を「母」一般に還元することも欲しない。ある種の一般的研究を読むと、それが私の状況に納得のいく形で適用できるということは私にもわかった。フロイト(『人間モーゼと一神教』)に註釈をほどこしつつ、J・J・グノーが説明するところによれば、ユダヤ教は、聖母崇拝の危険を避けるために偶像を排除したが、キリスト教は、母なる女性の表象を許すことによって「おきて」の厳しさを乗り越え、「想像的なもの」を受け入れたという。私は、偶像をもたず聖母を崇拝しない宗教(新教)に属しているが、しかしおそらく、文化的にはカトリック芸術によって培われてきたので、「温室の写真」を見て、「偶像」に、「想像的なもの」に帰依した、ということになるのである。それゆえ私は、自分に普遍性があることは理解できたのだが、しかし、理解したとはいいながら、どうしても割り切れない気持が残った。「母」一般のうちには、輝かしい、還元しえない一個の核、つまり、私の母が存在していたのである。
私は生涯母と一緒に暮してきたので、悲しみもまたひとしお深いのだ、と人は必ず思いたがる。しかし私の悲しみは、母があのような人であったことから来ているのである。母があのような人であったからこそ、私は母と一緒に暮してきたのである。母は「善」としての「母」であるうえに、さらに一個の人間としての魅力をそなえていた。プルーストの小説の「語り手」が祖母の死について言ったように、私もまたこう言うことができた。《私はただ単に苦しむというだけでなく、その苦しみの独自性をあくまで大事にしたかった》と。なぜなら、その独自性は、母のうちにある絶対に還元不可能なものの反映だったからである。そしてそれが、まさに還元不可能であるゆえに、一挙に、永遠に失われてしまったのだ。
喪は緩慢な作業によって徐々に苦悩を拭い去ると人は言うが、私にはそれが信じられなかったし、いまも信じられない。私にとっては、「時」は死別の悲しみを取り除いてくれる、ただそれだけにすぎないからである(私は単に死別したことを悲しんでいるのではない)。それ以外のことは、時がたっても、すべてもとのまま変わらない。というのも、私が失ったものは、一個の「形象」(「母」なるもの)ではなく、一個の人間だからである。いや、一個の人間ではなく、一個の特質(一個の魂)だからである。必要不可欠なものではなく、かけがえのないものだからである。私は「母」なしでも生きてゆくことができた(われわれはみな、遅かれ早かれそのようにしている)。しかし私に残された人生は、確実に、最後まで、形容しがたい(特質のない)ものとなることであろう。(ロラン・バルト『明るい部屋』花輪光訳 PP.90-92)
……たとえば、カフカは、《自分の不安を根絶する》ために、いいかえれば、《救いを得る》ために日記をつけた。私にはこの動機は自然とは思えない。少なくとも終始不変とは思えない。伝統的に「私的日記」に与える目的についても同様である。もはやそれが適切とは思えない。それは《誠実さ》(自分を語る、自分をさらけ出す、自分を裁く)の効用や威光と結びつけられてきた。しかし、精神分析、サルトルの底意批判、マルクス主義のイデオロギー批判が告白を空しいものとしてしまった。誠実さは第二度の想像物〔イマジネール〕でしかない。そうだ。(作品としての)「私的日記」を正当化する理由は、純粋な意味で、懐古的でさえある意味で、文学的でしかあり得ないだろう。(ロラン・バルト「省察」1979『テクストの出口』所収ーー痛みやすい果実)
「精神分析」とあるが、フロイトの《 私は自分の家の主人ではない(dass das Ich kein Herr sei in seinem eigenen Haus)》がまずはベースとなっている。
これについてはラカンの「愉快な」説明がある。
…教授連中にとって「我思う」が簡単に通用するのは、彼らがそこにあまり詳しく立ち止まらないからにすぎない。
「私は思う Je pense」に「私は嘘をついている Je mens」と同じだけの要求をするのなら次の二つに一つが考えられる。まず、それは「私は考えていると思っている Je pense que je pense」という意味。
これは想像的な、もしくは見解上の「私は思う」 、 「彼女は私を愛していると私は思う Je pense qu'elle m'aime」と言う場合に-つまり厄介なことが起こるというわけだが-言う「私は思う」以外の何でもない。
デカルトの「省察」の中でさえ、 「我思う」を、彼の言う根源的明証性はなにも保証することできない、 まさに想像的次元でしかないものにする遇有的事柄の多さに驚かされる。
もう一つの意味は「私は考える存在である Je suis un être pensant」である。この場合はもちろん、 「我思う」から自分の存在に対して思い上がりも偏見もない立場をまさに引き出そうとすることをそもそも台無しにすることになる。
私が「私はひとつの存在です Je suis un être」と言うと、それは「疑いもなく、私は存在にとって本質的な存在である Je suis un être essentiel à l'être, sans doute」ということで、ただのおもいあがりである。(ラカン、セミネールⅨ「同一化」向井雅明試訳からだが、一部変更)
ラカンは、言表内容の主体 sujet de l'énoncé と言表行為の主体 sujet de l'enonciation が一致している思い込んでいる人々のことを「私は私自身の主人maîtreである」という妄想的(パラノイア的)信念の言説--《m'être à moi même》(Lacan,S.17)ーーの主体としている。


