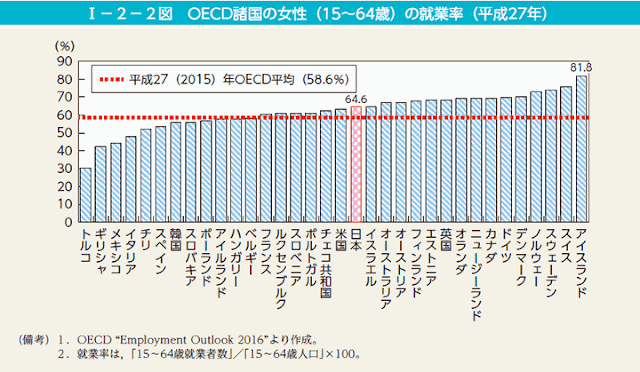いやあ無視してるわけじゃないんだけどな、美女に問われたら基本的にはお返事することにしてんだ。でも ラカンの「欲望のグラフ」ってのはボクは一度も触れたことがなくて、このグラフに対してこそ「無視」してんだ。
ここでは知っている範囲のことをーーというかほとんど今まで繰り返してきたことだが、それをほんの少しだけ欲望のグラフに関連づけて記すよ。
欲望のグラフ(le graphe du désir)は、セミネールⅤで初めて提示した図だけど、ここではセミネールⅩⅣから抜き出せば、こういうもんだな。
中期以降になれば、つまり「欲望のデフレ」があり欲望から享楽に移行してゆく観点からは、グラフの上左端にあるS(Ⱥ)が核心となってゆく。このマテームがラカンの思考の本来の焦点だ。
したがって簡潔に書けば、幻想の式[$ ◊ a]がS(Ⱥ)の上に乗る形になる。
より詳しく、四つの言説図の代表である「主人の言説」図を載せる書き方もある。
ラカンは先ほどのセミネールⅩⅣにおける「欲望のグラフ」へのコメントで、「長いあいだS(Ⱥ)をここに置いているが、たいしたことはコメントしてないな」などと言いつつ、S(Ⱥ) ≡ 過剰なる一者[l'« Un en trop »]としている。
|
Ici nous avons la marque, ou l'indice S(Ⱥ), que je n'ai pas… depuis des années qu'il existe, qu'il est placé dans ce graphe …sur lequel je n'ai pas porté tellement de commentaires. 〔・・・〕à cette place du graphe : S(Ⱥ), d'un signifiant, en tant qu'il concernerait, qu'il serait l'équivalent en quelque chose de ceci : de la présence de ce que j'ai appelé l'« Un en trop »… (Lacan, S14, 14 Décembre 1966) |
|
|
この過剰なる一者が、後に「一者がある」 y'a d'l'Unと言ったものに相当する。
この一者がある[y'a d'l'Un]、S2という知と関係しないS1、単独的な一者のシニフィアン[singulièrement le signifiant Un]、S2なきS1[S1 sans S2]こそ S(Ⱥ)と同じもの➡︎「固着マテーム:Σ ≡ S(Ⱥ) ≡ S1[S1 sans S2]」。
で、このS2なきS1[S1 sans S2]もしくはS(Ⱥ)が、欲動=享楽(サントーム)=固着=モノのマテーム。
|
斜線を引かれた大他者のシニフィアンS (Ⱥ)ーー、私は信じている、あなた方に向けてこのシンボルを判読するために、すでに過去に最善を尽くしてきたと。S (Ⱥ)というこのシンボルは、ラカンがフロイトの欲動を書き換えたものである[S de grand A barré [ S(Ⱥ)]ーーJe crois avoir déjà fait mon possible jadis pour déchiffrer pour vous ce symbole où Lacan transcrit la pulsion freudienne ](J.-A, Miller, LE LIEU ET LE LIEN, 6 juin 2001) |
|
|
|
シグマΣ、サントームのシグマは、シグマとしてのS(Ⱥ) と記される[c'est sigma, le sigma du sinthome, …que écrire grand S de grand A barré comme sigma] (J.-A. Miller, LE LIEU ET LE LIEN, 6 juin 2001) |
|
サントームという享楽自体 [la jouissance propre du sinthome] (J.-A. Miller, Choses de finesse en psychanalyse, 17 décembre 2008) |
|
|
|
サントームは固着である[Le sinthome est la fixation]. (J.-A. MILLER, L'Être et l'Un, 30/03/2011、摘要) |
|
ラカンがサントームと呼んだものは、ラカンがかつてモノと呼んだものの名、フロイトのモノの名である[Ce que Lacan appellera le sinthome, c'est le nom de ce qu'il appelait jadis la Chose, das Ding, ou encore, en termes freudiens](J.-A.MILLER,, Choses de finesse en psychanalyse X, 4 mars 2009) |
|
フロイトのモノを私は現実界と呼ぶ[La Chose freudienne …ce que j'appelle le Réel ](ラカン, S23, 13 Avril 1976) |
というわけで今のボクには「欲望のグラフ」を利用できることがあるなら、極論を言えばS(Ⱥ)だけだな。神経症者つまり大他者の信者向けだよ、欲望のグラフってのは。
|
そもそもこのS(Ⱥ)こそ、ひとりの女のシニフィアン、つまり穴の表象、蝦蟇口の表象なんだから。 |
|
ひとりの女はサントームである[une femme est un sinthome ](Lacan, S23, 17 Février 1976) |
|
別名、斜線を引かれた女性の享楽、神のシニフィアンだよ。 |
|
S(Ⱥ) にて示しているものは「斜線を引かれた女性の享楽」に他ならない。たしかにこの理由で、私は指摘するが、神はいまだ退出していないのだ。[S(Ⱥ) je n'en désigne rien d'autre que la jouissance de LȺ Femme, c'est bien assurément parce que c'est là que je pointe que Dieu n'a pas encore fait son exit. ](Lacan, S20, 13 Mars 1973) |
|
大他者はない。…この斜線を引かれた大他者のS(Ⱥ)…「大他者の大他者はある」という人間にとってのすべての必要性。人はそれを一般的に神と呼ぶ。だが、精神分析が明らかにしたのは、神とは単に女なるものだということである。il n'y a pas d'Autre[…]ce grand S de grand A comme barré [S(Ⱥ)]…La toute nécessité de l'espèce humaine étant qu'il y ait un Autre de l'Autre. C'est celui-là qu'on appelle généralement Dieu, mais dont l'analyse dévoile que c'est tout simplement « La femme ». (Lacan , S23, 16 Mars 1976) |
|
欲望のグラフなんかにかかずらあっておらずに、蝦蟇口に専念しろよ。 |
|
大他者のなかの穴のシニフィアンをS (Ⱥ) と記す[signifiant de ce trou dans l'Autre, qui s'écrit S (Ⱥ) ](J.-A. MILLER, - Illuminations profanes - 15/03/2006) |