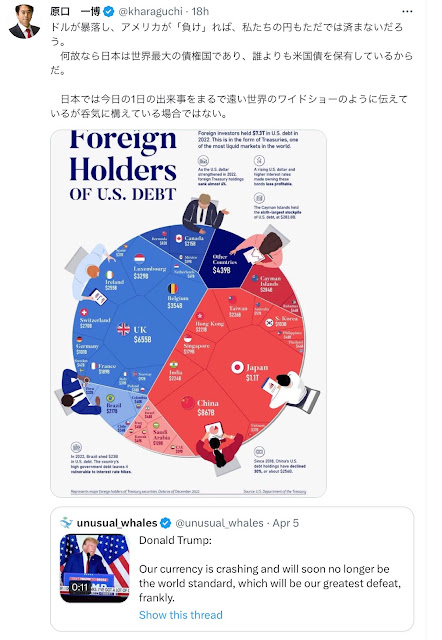この名古屋大学斎藤誠教授の言ったらしい《「そんなことは絶対起きて欲しくない」という人々の心理的な性向から往々にして思考停止に陥りがちになる》というのはいいね。
藤巻健史氏によって繰り返される円暴落の話の文脈での斎藤教授の言葉の引用だ。
とはいえ、である。藤巻健史氏はこう言いつつドルには絶対信任を置いているんだな、いまだに。それが不思議でならないね。
藤巻健史氏は、基軸通貨ドルの崩壊の可能性には「思考停止」になっているんじゃないかね、《「そんなことは絶対起きて欲しくない」という人々の心理的な性向から往々にして思考停止に陥りがちになる》に。別の言い方なら「選択的非注意」に。
|
古都風景の中の電信柱が「見えない」ように、繁華街のホームレスが「見えない」ように、そして善良なドイツ人の強制収容所が「見えなかった」ように「選択的非注意 selective inatension」という人間の心理的メカニズムによって、いじめが行われていても、それが自然の一部、風景の一部としか見えなくなる。あるいは全く見えなくなる。(中井久夫「いじめの政治学」1997年『アリアドネからの糸』所収)
|
|
戦争の準備に導く言葉は単純明快であり、簡単な論理構築で済む。人間の奥深いところ、いや人間以前の生命感覚にさえ訴える。誇りであり、万能感であり、覚悟である。これらは多くの者がふだん持ちたくて持てないものである。戦争に反対してこの高揚を損なう者への怒りが生まれ、被害感さえ生じる。仮想された敵に「あなどられている」「なめられている」「相手は増長しっ放しである」の合唱が起こり、反対者は臆病者、卑怯者呼ばわりされる。戦争に反対する者の動機が疑われ、疑われるだけならまだしも、何かの陰謀、他国の廻し者ではないかとの疑惑が人心に訴える力を持つようになる。
さらに、「平和」さえ戦争準備に導く言論に取り込まれる。すなわち第一次大戦のスローガ ンは「戦争をなくするための戦争」であり、日中戦争では「東洋永遠の平和」であった。戦争の否定面は「選択的非注意」の対象となる。「見れども見えず」となるのである。(中井久夫「戦争と平和についての観察」 2005年)
|
この「選択的非注意」は、藤巻氏に限らず、一般人以上に専門家と呼ばれる人々にことさら起きやすい気がするね。例えば、この1年間、国際政治学者の発言を観察したり、さらに2年前ぐらいからのウイルスあるいはワクチンに関わる医者たちの発言をいくらか観察した限りで、つくづくそう思ったよ。
専門家というより「信念の人」、そう言い直してもよい。
|
信念は牢獄である[Überzeugungen sind Gefängnisse]。それは十分遠くを見ることがない、それはおのれの足下を見おろすことがない。しかし価値と無価値に関して見解をのべうるためには、五百の信念をおのれの足下に見おろされなければならない、 ーーおのれの背後にだ・・・〔・・・〕
信念の人は信念のうちにおのれの脊椎をもっている。多くの事物を見ないということ、公平である点は一点もないということ、徹底的に党派的であるということ[Partei sein durch und durch]、すべての価値において融通がきかない光学[eine strenge und notwendige Optik in allen Werten] をしかもっていないということ。このことのみが、そうした種類の人間が総じて生きながらえていることの条件である。〔・・・〕
|
|
狂信家は絵のごとく美しい、人間どもは、根拠に耳をかたむけるより身振りを眺めることを喜ぶものである[die Menschheit sieht Gebärden lieber, als daß sie Gründe hört...](ニーチェ『反キリスト者』第54節、1888年)
|
もちろん私がこうニーチェを引用したのは「自戒」の意味もあるのであって、自ら常にこれに陥っていないか注意しなくちゃいけないということだ、それはても難しいとはいえ。
|
他人のなすあらゆる行為に際して自らつぎのように問うて見る習慣を持て。「この人はなにをこの行為の目的としているか」と。ただしまず君自身から始め、第一番に自分を取調べるがいい。(マルクス・アウレーリウス『自省録』神谷美恵子訳)
|
|
私は最近出会った室生犀星の言い方をとても好むね、《自分をあばくことで他をもほじくり返し、その生涯のあいだ、わき見もしないで自分をしらべ、もっとも身近かな一人の人間を見つづけてきた》という言い方を。
|
|
私といふ作家はその全作品を通じて、自分をあばくことで他をもほじくり返し、その生涯のあいだ、わき見もしないで自分をしらべ、もっとも身近かな一人の人間を見つづけてきたのである。(室生犀星「杏っ子」後書、1957年)
|