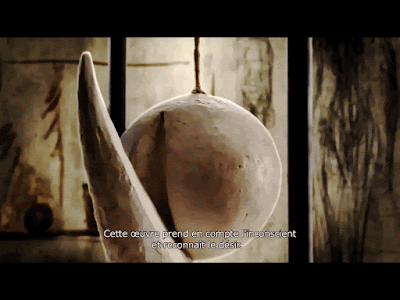死とは、私たちに背を向けた生の相であり、私たちが決して見ることのない生の相である。Der Tod ist die uns abgekehrte, von uns unbeschienene Seite des Lebens(リルケ書簡 Rainer Maria Rilke, Brief an Witold von Hulewicz vom 13. November 1925ーー「ドゥイノの悲歌」について)
この文の直後ーーここはハイデガーはなぜか引用していないーーに、《das größeste Bewußtsein unseres Daseins zu leisten》とあるので当然ではある(参照)。
そしてケレーニーである。
ゾーエー(永遠の生)は、タナトス(個別の生における死)の前提であり、この死もまたゾーエーと関係することによってのみ意味⋯⋯がある。死はその時々のビオス(個別の生)に含まれるゾーエーの産物なのである。(カール・ケレーニイ『ディオニューソス 破壊されざる生の根 』1976年)
このリルケとケレーニーの二文は「実は同じことを言っている」と主張するつもりは「今は」ない。
まずケレーニーの「ゾーエー/ビオス」ーー、ゾーエーを「剥き出しの生」としたアガンベン解釈とは全く異なるーーこの二語の基本的注釈を示しておかなくてはならない。
古代ギリシア語における「生」を表現する二つの語ーー「ゾーエーZoë」と「ビオス Bios」ーーとのあいだの本源的相違は次のように言いうる。
ゾーエーは永遠の生、無限の生である。ビオスは有限の生、個人の生である。ゾーエーは無限の「存在 being」であり、ビオスは、ゾーエーという永遠の世界の生死の顕現である。古代ギリシア研究者カール・ケレーニーKarl Kerenyiはこう説明している。
《ゾーエーはすべての個々のビオスをビーズのようにつないでいる糸のようなものである。そしてこの糸はビオスとは異なり、ただ永遠のものとして考えられるのである。》(カール・ケレーニイ『ディオニューソス.破壊されざる生の根』1976年)
これを「月」に関連づければ、ゾーエーは月の満ち欠けの全体の相となり、ビオスは個別の相となる。ゾーエーは超越的でありかつ内在的 transcendent and immanent である。ビオスはゾーエーの内在形態である。このように、ビオスはゾーエーのなかに包含されている。全体のなかに部分が含まれるように。(The Myth of the Goddess by Jules Cashford, Anne Baring, 1993)
月とある。月女神の「新月→満月→旧月」の循環原理とはゾーエーに他ならない。人はまずこれに気づかなければならない。ギリシア概念ゾーエーは、古代のあらゆる文明域にその相似形がある。
古代のある時期までのほとんどあらゆる(月)女神とは、「永遠の生=死」の女神である。
ほかにもたとえばフロイトは、女という「創造→維持→破壊」のトリアーデを示すシェイクスピア論を書いている。
月女神によって創造された無限に広がる大宇宙、無限に広がる大海原と「母なる大地」、そして、女性だけの能力の出産と育児、「有限の命(bios) 」を母から娘、娘から孫娘へと繋ぐ「無限の命(zoe) 」の神秘。「創造の言葉」logosから見離された男性たちはこの万物の創造のプロセスから完全に疎外されていた。「創造→維持→破壊」は、月母神、大地母神、母親だけの特権であった。宇宙原理、自然原理、女性原理の前に、男性たちは成す術が全く無かった。女性たちは、宇宙と大地と女性が、「創造→維持→破壊」の三相一体の母性力に従って連動しており、月女神がこの原理を支配していると信じていた。夜空で仰ぎ見る「新月→満月-旧月」の周期が、なによりのその証拠であった。
このようなものの見方、考え方、感受性の心の習慣(habitus mentalis)は、インドからヨーロッパの地域まで広がっていた。月女神のことを、例えばインドではKali Ma、ギリシアではEurynome、キプロスではAphrodite、ローマではLat. Luna, Venus. シリアではAstarte, Asherah、エジプトではIsisと呼び崇拝していた。(「古代母権制社会研究の今日的視点 一 神話と語源からの思索・素描」松田義幸・江藤裕之、2007年)
古代のある時期までのほとんどあらゆる(月)女神とは、「永遠の生=死」の女神である。
ほかにもたとえばフロイトは、女という「創造→維持→破壊」のトリアーデを示すシェイクスピア論を書いている。
ここ(シェイクスピア『リア王』)に描かれている三人の女たちは、生む女 Gebärerin、パートナー Genossin、破壊者としての女 Vẻderberin であって、それはつまり男にとって不可避的な、女にたいする三通りの関係である。あるいはまたこれは、人生航路のうちに母性像が変遷していく三つの形態であることもできよう。
すなわち、母それ自身 Mutter selbstと、男が母の像を標準として選ぶ愛人Geliebte, die er nach deren Ebenbild gewähltと、最後にふたたび男を抱きとる母なる大地 Mutter Erde である。
そしてかの老人は、彼が最初母からそれを受けたような、そういう女の愛情をえようと空しく努める。しかしただ運命の女たちの三人目の者、沈黙の死の女神 schweigsame Todesgöttin のみが彼をその腕に迎え入れるであろう。(フロイト『三つの小箱』1913年)
そしてドゥルーズもマゾッホ論で、ニーチェの師バハオーフェンに触れつつ、このフロイトのトリアーデを示しているのである。これにいまだ冷感症のインテリ諸君は、そうそうに永遠の生の世界へと撤退すべきである。そうすれば冷感症はいくらか是正される筈である。
もっとも彼らの眠る場所にはキクラデス女神はもったいない。コケシ程度でよろしい。
ところでゾーエーに関してケレーニー派の木村敏はこう言っている。
わたしがケレーニイから学んだことは、ゾーエーというのはビオスをもった個体が個体として生まれてくる以前の生命だということです。ケレーニイは「ゾーエーは死を知らない」といいますが、そして確かにゾーエーは、有限な生の終わりとしての「死」は知らないわけですが、しかしゾーエー的な生ということをいう場合、わたしたちはそこではまだ生きていないわけですよね。ビオス的な、自己としての個別性を備えた生は、まだ生まれていない。そして私たちが自らのビオスを終えたとき、つまり死んだときには、わたしたちは再びそのゾーエーの状態に帰っていくわけでしょう。
だからわたしは、このゾーエーという、ビオスがそこから生まれてきて、そこに向かって死んでいくような何か、あるいは場所だったら、それを「生」と呼ぼうが「死」と呼ぼうが同じことではないかと思うわけです。ビオス的な個人的生命のほうを「生」と呼びたいのであれば、ゾーエーはむしろ「死」といったほうが正解かもしれない。(木村敏 『臨床哲学の知-臨床としての精神病理学のために』2008年)
木村敏はこの論で、「ゾーエーはエスと重なる、グロデックが「生命の根源」という意で用いたエスと重なる」という意味合いのこととも言っている。グロデックは、もちろんニーチェのエスとフロイトのエスを架橋した人物である。
いま、エスは語る、いま、エスは聞こえる、いま、エスは夜を眠らぬ魂のなかに忍んでくる、nun redet es, nun hört es sich, nun schleicht es sich in nächtliche überwache Seelen:(ニーチェ「酔歌」『ツァラトゥストラ』)
フロイトは以下の文で、ニーチェの「権力への意志 Willen zur Macht」ーークロソウスキーが示した「至高の欲動 impulsion suprême」ーーの Macht という語さえ使ってエスを語っている。
エスの力能( 権力Macht)は、個々の有機体的生の真の意図 Einzelwesens を表す。それは生得的欲求 Bedürfnisse の満足に基づいている。己を生きたままにすること、不安の手段により危険から己を保護すること、そのような目的はエスにはない。それは自我の仕事である。…
エスの欲求によって引き起こされる緊張 Bedürfnisspannungen の背後にあると想定された力 Kräfte は、欲動 Triebe と呼ばれる。欲動は、心的な生 Seelenleben の上に課される身体的要求 körperlichen Anforderungen を表す。(フロイト『精神分析概説』草稿、死後出版1940年)
そしてニーチェにはツァラトゥストラののグランフィナーレには決定的な文がある。
おまえたちは、かつて享楽にたいして「然り」と言ったことがあるか。おお、わたしの友人たちよ、そう言ったことがあるなら、おまえたちはいっさいの苦痛にたいしても「然り」と言ったことになる。すべてのことは、鎖によって、糸によって、愛によってつなぎあわされているのだ。
Sagtet ihr jemals ja zu Einer Lust? Oh, meine Freunde, so sagtet ihr Ja auch zu _allem_ Wehe. Alle Dinge sind verkettet, verfädelt, verliebt, -
……いっさいのことが、新たにあらんことを、永遠にあらんことを、鎖によって、糸によって、愛によってつなぎあわされてあらんことを、おまえたちは欲したのだ。おお、おまえたちは世界をそういうものとして愛したのだ、――
- Alles von neuem, Alles ewig, Alles verkettet, verfädelt, verliebt, oh so _liebtet_ ihr die Welt, - (ニーチェ『ツァラトゥストラ』酔歌 )
これをケレーニーの次の文と読み比べれば、もはや何もいいたくなくなる。
ゾーエーはすべての個々のビオスをビーズのようにつないでいる糸のようなものである。そしてこの糸はビオスとは異なり、ただ永遠のものとして考えられるのである。(カール・ケレーニイ『ディオニューソス.破壊されざる生の根』1976年)
ーーすべての解はニーチェにありき。
学者とはニーチェの酔歌における「lust」をわたくしが「享楽」と訳したことにごねる種族である。その学者さん方々の頭に刺激を与えるために、lustをリビドーと訳したってよろしい、「おまえたちは、かつてリビドーに対して然りと言ったことがあるか」と。あるいはゾーエーの代りにリビドーを代入したってよろしい。「リビドーとは個々のビオスをビーズのようにつないでいる糸のようなものである」と。
学問的に、リビドーLibido という語は、、日常的に使われる語のなかでは、ドイツ語の「快 Lust」という語がただ一つ適切なものではあるが、残念なことに多義的であって、欲求 Bedürfnisses の感覚と同時に満足 Befriedigungの感覚を呼ぶのにもこれが用いられる。(フロイト『性欲論』1905年ーー1910年註)
ところで「ゾーエー(永遠の生)とエスは重なる」とする木村敏、あのラカンをひどく嫌う木村だが(気持ちはわからないでもない)、ラカンは、リビドー は「不死の生」だと言っている。リビドーとはもちろんエスとほとんど等価の概念である。木村はラカンと同じことを言っているのである。
リビドー libido 、純粋な生の本能 pur instinct de vie としてのこのリビドーは、不死の生vie immortelleである。…この単純化された破壊されない生 vie simplifiée et indestructible は、人が性的再生産の循環 cycle de la reproduction sexuéeに従うことにより、生きる存在から控除される soustrait à l'être vivant。(ラカン、S11, 20 Mai 1964)
リビドーは不死の生、すなわち永遠の生であり、フロイトにとってはプラトンのエロスである。
リビドーは情動理論 Affektivitätslehre から得た言葉である。…
われわれは、この欲動エネルギー Energie solcher Triebe をリビドーLibido と呼んでいるが、それは愛Liebeと総称されるすべてのものを含んでいる。
……哲学者プラトンのエロスErosは、その由来 Herkunft や作用 Leistung や性愛 Geschlechtsliebe との関係の点で精神分析でいう愛の力 Liebeskraft、すなわちリビドーLibido と完全に一致している。…
この愛の欲動 Liebestriebe を、精神分析ではその主要特徴と起源からみて、性欲動 Sexualtriebe と名づける。(フロイト『集団心理学と自我の分析』1921年)
リビドー とは「エロスエネルギー」とも表現される。
すべての利用しうるエロスのエネルギーEnergie des Eros を、われわれはリビドーLibidoと名付ける。…(破壊欲動のエネルギーEnergie des Destruktionstriebesを示すリビドーと同等の用語はない)。(フロイト『精神分析概説』死後出版1940年)
現在になっても日本学者ムラではまったく理解されていないが、エロス欲動とは、「永遠の生=死」、つまりゾーエーに向かう動きである。他方、タナトス欲動とは、「個別の生(ビオス)」に向かう動きである。これが(古臭い通念とは異なった)真の「エロス/タナトス」である。つまり、最晩年のフロイトが「エロス /タナトス」を「融合/分離」、「引力/斥力」と言っている内実に他ならない(参照:「エロス欲動という死の欲動」)。
ところでフロイト寄りのラカン派ポール・バーハウは、21世紀に入ってからの三つの論文で、ゾーエーとビオスに触れている。彼の最終的結論はこうである。
フロイトのエロスはゾーエー欲動であり、タナトスはビオス欲動である。
Freud's Eros is a Zoë drive, and Thanatos is a bios drive. (ポール・バーハウ Paul Verhaeghe、Phallacies of binary reasoning: drive beyond gender 2004)
この文だけでは(即座の理解のためには)やや難があるが、この豊かな示唆をもった文を、「原エロス」という造語を使ってわたくしなりに解きほぐせばこうなる。
上辺(分子)が示すのは、まず第一に、人はみな永遠の生=死の引力に誘引される動きをするということである。これがエロス欲動(ゾーエー欲動)である。だが分母(母胎)にある原エロスに魅惑されつつもその死の相に戦慄し斥力が働く。これがタナトス欲動(ビオス欲動)である。このエロスとタナトスの欲動融合が人間の生の姿である。
実はラカンの享楽も死である。すくなくとも原享楽は死である。
死への道は、享楽と呼ばれるもの以外の何ものでもない。le chemin vers la mort n’est rien d’autre que ce qu’on appelle la jouissance (ラカン、S17、26 Novembre 1969ーー「究極のエロス・究極の享楽とは死のことである」)
そして享楽はリビドーである。
ラカンは、フロイトがリビドーとして示した何ものか quelque chose de ce que Freud désignait comme la libido を把握するために仏語の資源を使った。すなわち享楽 jouissance である。(Miller, L'Être et l'Un, 30/03/2011)
ヒエロニムス・ボスの「悦楽の園 Tuin der lusten」とは、実は「リビドーの園」、「享楽の園」のことである。
厳密に記せば話が長くなるので、これ以上は記さないでおくが、ここでの話題であるケレーニを基盤とした図ぐらいは示しておこう。
こうしてケレーニー、フロイト、ラカン、そして木村敏は瞭然と繋がるのである。
ーーケレーニイはドイツ語で書いてから、英語でも書いているのだが、上の箇所の英文は「Dionysos: Archetypal Image of Indestructible Life Carl Kerenyi、pdf」にある。
実は1960年代のドゥルーズも似たようなことを言っているのである。ただしドゥルーズの使う用語が、日本学者ムラのセンセたちにはまったく理解されていないようで、ネット上で二人の関西系ドゥルーズ派のエライセンセがゾーエーに触れているのを見てしまったが、まったく頓珍漢でドゥルーズの洞察につなげる気は毛ほどもないらしい・・・
ドゥルーズはマゾッホ論で「死の欲動 pulsions de mort」と「死の本能 Instinct de mort 」を区別している(参照)。核心はこれである。ドゥルーズ自身、どうせわかっちゃもらえないと思ったのか、マゾッホ論以降、--プルースト論でこの区分を匂わせる以外はーー示していない不幸はあるが。
彼の三つの論文のエロス/タナトスの捉え方はこうである。
三区分があったり二区分があったりして即座にビオス/ゾーエーの観点と繋がらないように一見みえるが、マゾッホ論の「欲動混淆」の箇所に「ビオス」、「超越論的原理」の箇所に「ゾーエー」を代入すれば、一丁上がりである。
こうしてケレーニー、フロイト、ラカン、そして木村敏は瞭然と繋がるのである。
ビオスと死(タナトス)との関係は、一方の死を排除してしまうような対立状態にはない。そうではなく、特徴的な死は特徴的な生の一部なのである。そればかりか、生はみずからの活動を停止する仕方によってさえも特徴づけられる。あるギリシャ語の言い回しは、<独自の死によって生を終える>ことが特徴ある死であると述べて、この点を実に端的に言い表している。それとは逆に、タナトスをしめ出す生がギリシャ語のゾーエーである。
ゾーエーにもし輪郭があるとしてもそれは稀であるが、その代わりにゾーエーは、死すなわちタナトスとことのほか対立的な関係にある。ゾーエーから明瞭に <ひびく>ところのものは< 非死>である。それは死を自分に近寄せない何ものかである。(カール・ケレーニイ『ディオニューソス.破壊されざる生の根 』1976年)
ーーケレーニイはドイツ語で書いてから、英語でも書いているのだが、上の箇所の英文は「Dionysos: Archetypal Image of Indestructible Life Carl Kerenyi、pdf」にある。
実は1960年代のドゥルーズも似たようなことを言っているのである。ただしドゥルーズの使う用語が、日本学者ムラのセンセたちにはまったく理解されていないようで、ネット上で二人の関西系ドゥルーズ派のエライセンセがゾーエーに触れているのを見てしまったが、まったく頓珍漢でドゥルーズの洞察につなげる気は毛ほどもないらしい・・・
ドゥルーズはマゾッホ論で「死の欲動 pulsions de mort」と「死の本能 Instinct de mort 」を区別している(参照)。核心はこれである。ドゥルーズ自身、どうせわかっちゃもらえないと思ったのか、マゾッホ論以降、--プルースト論でこの区分を匂わせる以外はーー示していない不幸はあるが。
彼の三つの論文のエロス/タナトスの捉え方はこうである。
三区分があったり二区分があったりして即座にビオス/ゾーエーの観点と繋がらないように一見みえるが、マゾッホ論の「欲動混淆」の箇所に「ビオス」、「超越論的原理」の箇所に「ゾーエー」を代入すれば、一丁上がりである。
でももうやめておこう、精神の中流階級を相手にしても致し方ないのである。
肝腎なのは精神の貴族階級ではなく、精神の下層階級として、リビドーの園を憧憬し、月女神の彫像や母なる大地をじっくり愛でることである。
ところで墓の語源であるギリシア語 tumbos とラテン語 tumulus は、「膨れる、受胎している」という意味のラテン語 tumere と同語源であるのを御存知だろうか。すなわち墓とは子宮のことである。
ここでもう一つ、ゾーエーとビオスのヴァリエーションを示しておこう。
中井久夫は安永浩のファントム空間をめぐって次の図を示している。
上の図は容易に次のように示し直せる。
学者というものは、精神の中流階級に属している以上、真の「偉大な」問題や疑問符を直視するのにはまるで向いていないということは、階級序列の法則から言って当然の帰結である。加えて、彼らの気概、また彼らの眼光は、とうていそこには及ばない。(ニーチェ『悦ばしき知識』1882年)
肝腎なのは精神の貴族階級ではなく、精神の下層階級として、リビドーの園を憧憬し、月女神の彫像や母なる大地をじっくり愛でることである。
ところで墓の語源であるギリシア語 tumbos とラテン語 tumulus は、「膨れる、受胎している」という意味のラテン語 tumere と同語源であるのを御存知だろうか。すなわち墓とは子宮のことである。
ここでもう一つ、ゾーエーとビオスのヴァリエーションを示しておこう。
以前の状態を回復しようとするのが、事実上、欲動 Triebe の普遍的性質である。 Wenn es wirklich ein so allgemeiner Charakter der Triebe ist, daß sie einen früheren Zustand wiederherstellen wollen, (フロイト『快原理の彼岸』1920年)
人には、出生 Geburtとともに、放棄された子宮内生活 aufgegebenen Intrauterinleben へ戻ろうとする欲動 Trieb、⋯⋯母胎Mutterleib への回帰運動(子宮回帰 Rückkehr in den Mutterleib)がある。(フロイト『精神分析概説』草稿、死後出版1940年)
中井久夫は安永浩のファントム空間をめぐって次の図を示している。
安永(安永浩)と、生涯を通じてのファントム空間の「発達」を語り合ったことがある。簡単にいえば、自極と対象極とを両端とするファントム空間軸は、次第に分化して、成年に達してもっとも離れ、老年になってまた接近するということになる。(中井久夫「発達的記憶論」初出2002年『徴候・記憶・外傷』所収)
上の図は容易に次のように示し直せる。
⋯⋯⋯⋯
さて最後に冒頭のリルケ、「死とは、私たちに背を向けた生の相であり、私たちが決して見ることのない生の相である」に戻ろう。
この文は、ドゥイノの悲歌を読み込めば、こう言い換えうるのではないか。
すなわち、「永遠の生である死(ゾーエー)とは、私たちに背を向けたビオスの彼岸の相であり、この無限の生であるゾーエーは、私たちが決して見ることのない個別の生(ビオス)の彼岸にある永遠の相である」と。
あるいはマルテに戻ってもよい。
と引用したら、蚊居肢子の偏愛の対象キクラデス女神像をまたまた貼り付けざるをえない。なぜあの時代の多くの死者たちは、この彫像と一緒に埋められたのかは、もはや言うまでもなかろう。ゾーエー(永遠の生)とともに埋葬されたのである。
これはおそらく古代であればどこもかしこも似たようなことがなされていた筈である。たとえばわが縄文土器の多くには女陰や妊娠の形態の徴がある。
さて最後に冒頭のリルケ、「死とは、私たちに背を向けた生の相であり、私たちが決して見ることのない生の相である」に戻ろう。
この文は、ドゥイノの悲歌を読み込めば、こう言い換えうるのではないか。
すなわち、「永遠の生である死(ゾーエー)とは、私たちに背を向けたビオスの彼岸の相であり、この無限の生であるゾーエーは、私たちが決して見ることのない個別の生(ビオス)の彼岸にある永遠の相である」と。
「第一の悲歌」より
天使たちは(言いつたえによれば)しばしば生者たちのあいだにあるのと
死者たちのあいだにあるのとの区別を気づかぬという。永劫の流れは
生と死の両界をつらぬいて、あらゆる世代を拉し、
それらすべてをその轟音のうちに呑み込むのだ。
Engel (sagt man) wüßten oft nicht, ob sie unter
Lebenden gehn oder Toten. Die ewige Strömung
reißt durch beide Bereiche alle Alter
immer mit sich und übertönt sie in beiden.
あるいはマルテに戻ってもよい。
・昔は誰でも、果肉の中に核があるように、人間はみな死が自分の体の中に宿っているのを知っていた。
・女が孕んで、立っている姿は、なんという憂愁にみちた美しさであったろう。ほっそりとした両手をのせて、それとは気づかずにかばっている大きな胎内には、二つの実が宿っていた、嬰児と死が。広々とした顔にただようこまやかな、ほとんど豊潤な微笑は、女が胎内で子供と死とが成長していることをときどき感じたからではないか。(リルケ『マルテの手記』)
と引用したら、蚊居肢子の偏愛の対象キクラデス女神像をまたまた貼り付けざるをえない。なぜあの時代の多くの死者たちは、この彫像と一緒に埋められたのかは、もはや言うまでもなかろう。ゾーエー(永遠の生)とともに埋葬されたのである。
これはおそらく古代であればどこもかしこも似たようなことがなされていた筈である。たとえばわが縄文土器の多くには女陰や妊娠の形態の徴がある。