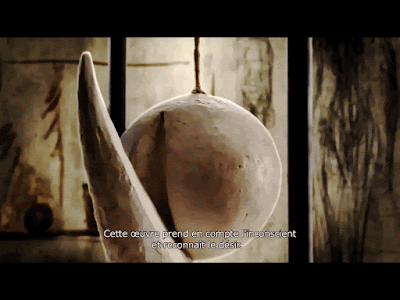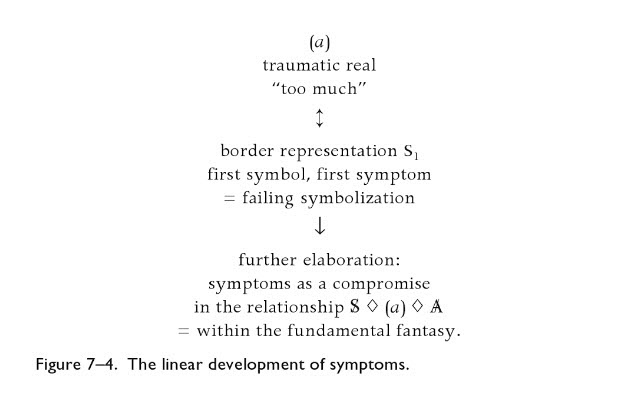小林秀雄1902
坂口安吾1906
中原中也1907
大岡昇平1909
坂本睦子1915(大岡『花影』のモデル)
ーーなんだな、文壇史にはまったく疎いのだが。
坂本睦子Wikiの項にはこうある(信憑性のほどは知らない)。
静岡県三島市生まれ。孤児同然に育った不幸な生い立ちで、1930年、銀座のバー「はせ川」へ女給として出て、直木三十五に口説かれて処女を奪われたという。1931年、青山二郎が出資した銀座のバー「ウィンゾア」に出て、坂口安吾と中原中也が彼女を争ったという。その後、1932年から1936年まで安吾の愛人だったとされるが、菊池寛にも庇護され、小林秀雄に求婚されて、いったんは受け入れたが睦子が破棄し、オリンピックの選手と京都へ駆け落ちしたという。
その後東京へ戻り、番衆町の喫茶店「欅」に勤めたあと、1935年、工場主をパトロンとして銀座に「アルル」という自分の店を持った。時に二十歳。1938年頃から河上徹太郎の愛人となって長く続いた。戦後、1947年からまた銀座へ出て、バー「ブーケ」で働く。1949年には、青山二郎が睦子のアパートに住んでいたこともある。1950年、青山が命名した「風(プー)さん」が開店し、ここに勤めている時、作家としてデビューしたての大岡昇平と関係ができ、大岡のアメリカ留学を挟んで八年近く愛人関係にあった。その後睦子は「ブーケ」の支店「ブンケ」に出ている。しかしために大岡は夫人の自殺未遂のようなことがあって何度か別れを考えたという。
ほかの情報源としては、久世光彦が坂本睦子をモデルにして「女神」という小説(2003年)を書いているそうだ(
参照)。
彼女の写真を検索すると、次の画像に行き当たる。
ーーということは若いころは右上の少女だったんだろう、たぶん。
《1932年から1936年まで安吾の愛人だったとされる》とwikiにはあるが、果たしてどうなんだろう? ちょっとはっきりしたことは分からない。
ただし《1931年、青山二郎が出資した銀座のバー「ウィンゾア」に出て、坂口安吾と中原中也が彼女を争った》というのは、安吾がーーあくまで「小説」のなかの記述だがーーたしかにそう記している。
1931年とは、1915年生れの坂本睦子の16歳のときということになる。安吾曰く《この娘は十七であつた》。
以下、坂口安吾『二十七歳』から抜き出す。
そのころ、春陽堂から「文科」といふ半職業的な同人雑誌がでた。牧野信一が親分格で、小林秀雄、嘉村礒多、河上徹太郎、中島健蔵、私などが同人で、原稿料は一枚五十銭ぐらゐであつたと思ふ。五十銭の原稿料でも、原稿料のでる雑誌などは、大いに珍らしかつたほど、不景気な時代であつた。五冊ほどで、つぶれた。私は「竹藪の家」といふのを連載した。
この同人が行きつけの酒場があつた。ウヰンザアといふ店で、青山二郎が店内装飾をしたゆかりで、青山二郎は「文科」の表紙を書き、同人のやうなものでもあつたせゐらしい。
ある夜更け、河上と私がこの店の二人の女給をつれて、飲み歩き、河上の家へ泊つたことがある。河上は下心があつたので、女の一人をつれて別室へ去つたが、残された私は大いに迷惑した。なぜなら、実は私も河上の連れ去つた娘の方にオボシメシがあつたからで、残された女は好きではない。オボシメシと云つても、二人のうちならそつちが好きといふだけのことではあるが、当時私はウブだから、残された女が寝ませうよと言ふけれどもその気にならない。そのうちに河上が、すんだかい、と言つて顔をだした。彼は娘にフラレたのである。俺はフラレた、と言つて、てれて笑ひながら、娘と手をくんで、戻つてきた。この娘は十七であつた。
その翌朝、河上の奥さんが憤然と、牛乳とパンを捧げて持つてきてくれたが、シラフで別れるわけにも行かず、四人で朝からどこかで飲んで別れたのだが、そのとき、実は俺はお前の方が好きなんだと十七の娘に言つたら、私もよ、と云つて、だらしなく仲がよくなつてしまつたのである。
この娘はひどい酒飲みだつた。私がこんなに惚れられたのは珍らしい。八百屋お七の年齢だから、惚れ方が無茶だ。私達はあつちのホテル、こつちの旅館、私の家にまで、泊り歩いた。泊りに行かうよ、連れて行つてよ、と言ひだすのは必ず娘の方なので、私たちは友達のカンコの声に送られて出発するのであるが、私とこの娘とは肉体の交渉はない。娘は肉体に就て全然知識がないのであつた。
私は処女ではないのよ、と娘は言ふ。そのくせ処女とは如何なるものか、この娘は知らなかつた。愛人、夫婦は、たゞ接吻し、同じ寝床で、抱きあひ、抱きしめ、たゞ、さう信じ、その感動で、娘は至高に陶酔した。肉体の交渉を強烈に拒んで、なぜそんなことをするのよ、と憤然として怒る。まつたく知らないのだ。
そのくせ、たゞ、単に、いつまでも抱きあつてゐたがり、泊りに行きたがり、私が酒場へ顔を見せぬと、さそひに来て、娘は私を思ふあまり、神経衰弱の気味であつた。よろよろして、きりもなく何か口走り、私はいくらか気味が悪くなつたものだ。肉体を拒むから私が馬鹿らしがつて泊りに行かなくなつたことを、娘は理解しなかつた。
中原中也はこの娘にいさゝかオボシメシを持つてゐた。そのときまで、私は中也を全然知らなかつたのだが、彼の方は娘が私に惚れたかどによつて大いに私を咒つてをり、ある日、私が友達と飲んでゐると、ヤイ、アンゴと叫んで、私にとびかゝつた。
とびかゝつたとはいふものの、実は二三米離れてをり、彼は髪ふりみだしてピストンの連続、ストレート、アッパーカット、スヰング、フック、息をきらして影に向つて乱闘してゐる。中也はたぶん本当に私と渡り合つてゐるつもりでゐたのだらう。私がゲラ〳〵笑ひだしたものだから、キョトンと手をたれて、不思議な目で私を見つめてゐる。こつちへ来て、一緒に飲まないか、とさそふと、キサマはエレイ奴だ、キサマはドイツのヘゲモニーだと、変なことを呟きながら割りこんできて、友達になつた。非常に親密な友達になり、最も中也と飲み歩くやうになつたが、その後中也は娘のことなど嫉く色すらも見せず、要するに彼は娘に惚れてゐたのではなく、私と友達になりたがつてゐたのであり、娘に惚れて私を憎んでゐるやうな形になりたがつてゐたゞけの話であらうと思ふ。
オイ、お前は一週に何度女にありつくか。オレは二度しかありつけない。二日に一度はありつきたい。貧乏は切ない、と言つて中也は常に嘆いてをり、その女にありつくために、フランス語個人教授の大看板をかゝげたり、けれども弟子はたつた一人、四円だか五円だかの月謝で、月謝を貰ふと一緒に飲みに行つて足がでるので嘆いてをり、三百枚の飜訳料がたつた三十円で嘆いてをり、常に嘆いてゐた。彼は酒を飲む時は、どんなに酔つても必ず何本飲んだか覚えてをり、それはつまり、飲んだあとで遊びに行く金をチョッキリ残すためで、私が有金みんな飲んでしまふと、アンゴ、キサマは何といふムダな飲み方をするのかと言つて、怒つたり、恨んだりするのである。あげくに、お人好しの中島健蔵などへ、ヤイ金をかせ、と脅迫に行くから、健蔵は中也を見ると逃げだす始末であつた。(坂口安吾『二十七歳』1947年)
安吾はこう記したあと、しばらくして次のように書いている。
私はすでにその前に、矢田さんと結婚したいといふことを母に言つた。母も即座にうなづいてゐたが、やがて日数へて、いつ結婚するか、といふ。私は胸をしめつけられて、返事ができず、やうやく声がでるやうになると、もう厭なんだ、やめたんだ、と答へて席を立つた。
然し、三日にあげず手紙が来てゐるのだから、母は私の言葉を痴話喧嘩ぐらゐにしか受けとらず、あるとき親戚の者がきたとき、私を指して、今度、矢田津世子と結婚するのだ、と言ふ。嘘だ! 結婚しないと言つてゐるのに! 私は唐突に叫んだ。叫ぶことが、無我夢中であつた。私の血は逆流してゐた。私は母の淋しい顔を思ひだす。
その頃だつた。例の十七の娘が、神経衰弱の如くになつて、足もとをフラ〳〵させ、私を訪ねてきて、酒を飲みに行かうよ、お金は私が持つてゐるから、と言ふ。暮れがたであつた。私は仕事があつて今夜は酒がのめないからと嘘をつき、ともかく、そのへんまで送らうと一緒に歩くと、女は憑かれたやうにとりとめもなく口走り、せつなげな笑ひが仮面のやうにその顔にはりついてゐる。そのうちに、ふと、知つてるわ、矢田さんに惚れたんでせう、と言つた。恨む声ではなかつた。せつなげな笑ひが、まだ、はりついてゐた。気象の激しい娘であつた。モナミだか千疋屋だかで、テーブルの上のガラスの瓶をこはしたことがある。ボーイがきて、六円いたゞきます、と言ふ。娘は十二円ボーイに渡して、隣のテーブルの花瓶をとると、エイと土間に叩きつけて、ミヂンにわつて、サヨナラと出てきた。さういふ気象を知つてゐる私であるから、私に対する娘のあまりのか弱さに、私は暗然たる思ひもあつた。
「片思ひなの?」
娘は私の顔をのぞいた。それは、優しい心によつて語られた、愛情にみちた言葉であつた。恨む心はミヂンもなく、いたはる心だけなのだ。私は答へる言葉もなく、答へたい心もなかつた。
このへんで別れようと私が言ふと、ウン、娘はうなづいて、私の手を握り、まだつゞいてゐるあの切なげな笑ひで、仕事がすんだら、又、のまうよね、さう言つて、娘は手をふり、素直に闇の底へ消えてしまつた。これが娘と私との最後の別れであつた。(坂口安吾『二十七歳』1947年)
この「自伝小説」のなかの記述を「事実」として取り扱うことが許されるなら、坂本睦子が《1932年から1936年まで安吾の愛人だった》ということはない。
⋯⋯⋯⋯
安吾は少年時代、インターハイの高跳びで優勝している。そして、はたち前後に坊主を目指している、――《私はすでに二十の年から、最も屡々世を捨てることを考え、坊主になろうとし⋯⋯》(「三十歳」)ーー、その前には一年ほど代用教員もしている(すばらしい教師だったようだ)。
私が教員をやめるときは、ずいぶん迷った。なぜ、やめなければならないのか。私は仏教を勉強して、坊主になろうと思ったのだが、それは「さとり」というものへのあこがれ、その求道のための厳しさに対する郷愁めくものへのあこがれであった。教員という生活に同じものが生かされぬ筈はない。私はそう思ったので、さとりへのあこがれなどというけれども、所詮名誉慾というものがあってのことで、私はそういう自分の卑しさを嘆いたものであった。(坂口安吾「風と光と二十の私と」)
長身のいい男だったろうが、「情痴作家」と呼ばれたイメージに反し、《私は二十七まで童貞だった》のは、安吾の少年期から青春期のおどろくべき純粋さーーそして《屡々世を捨てることを考え、坊主になろうとし》た事ーーに思いを馳せれば何の不思議でもない。
二十の時、一人の山登りに、谷底へ墜落、落ちて行く時、オヤオヤ死ぬな、と思った。悲しくなかった。ほんとだ。そしたら程へて気がついた。谷川の中で、私は水の上へ首だけだしていた。ふくらんだリュックのおかげであった。
二十一の時、本を読みながら市内電車から降りたら自動車にハネ飛ばされたが、宙にグルグル一回転、頭を先に落っこったが、私は柔道の心得があり、先に手をつきながら落ちたので、頭の骨にヒビができただけで、助かった。
私は二十七まで童貞だった。
二十七か八のころから三年ほど人の女房だった女と生活したが、これからはもう散々で、円盤ややりや自動車の比ではない。窒息しなかったのが不思議至極で、思いだしても、心に暗幕がはられてしまう。
その後はなるべく危険に遠ざかるよう心がけて今日まで長生きしてきたが、この心がけは要するに久米の仙人で、常日ごろ生命の危険におびやかされ通しでいるのは白状しなくともお分りだろう。
お酒は二十六から飲んだが、通算して、まだ十五石ぐらいのものだろう。(坂口安吾「てのひら自伝」1947年 )
ーー《二十七か八のころから三年ほど人の女房だった女と生活した》とあるが、これは、わたくしの知る限りでは、安吾の小説にはその名は出現しないが、自伝小説「いづこへ」の女であり、ネット上から情報を拾う範囲では、酒場「ボヘミアン」のマダムお安さんと呼ばれる方だそうだ。
⋯⋯⋯⋯
安吾の少年期から青春期のおどろくべき純粋さ、と上に記したが、青春期の真の友だっただろう、菱山修三について次のように記している。
読書は愛好者としてでなければ、学研的なそれであることが多い。稀に血と肉を賭けて読む場合もあるが、菱山修三のヴァレリイに至つては、ひと頃の彼の歴史と、生活と、それに感覚も生命も、その全てを賭け、彼自身ヴァレリイの中に発育した。彼はその宿命さへ賭けてゐたかに見えてゐた。それは、純一無垢、多感極まりない少年にのみ許された唯一の至高な場合であつて、あの頃、菱山はその至高な少年であつた。
我々は結局二人の少年であり得ない。そして私は、私も嘗て一人の少年であつたが、菱山のやうな無類の激しさで一先人に血と肉を、その宿命を賭けるほどの、生死を通した読書の機会は遂ひに持たずに少年を終つた。私は今も落莫として己れの影を見失ひ、我れを見凝める厳粛な純情を暗闇の幕の彼方へ彷徨はせてゐる。(坂口安吾「宿命の CANDIDE」1933年)
⋯⋯⋯⋯
ヴァレリー「オルフェ」(菱山修三訳)
……私は心の内で組み立てる、桃金嬢(ミルト)の下で、あの素晴らしいオルフェを!
火花が降つて来る、かずかずの純粋(きよらか)な円形の谷々から。
彼は替へる、禿げ山を、
神の眼覚しい仕業(しわざ)の輝く荘厳な戦捷のしるしに。
神が歌ふならば、十全の風景を引き裂く。
太陽も眼のあたり石また石の動揺の、空怖ろしさを見てしまふ。
嘗て耳にしたこともない哀訴の声が、聖堂の和やかな黄金(きん)の
眼くるめくばかり輝く高い壁を、呼び寄せる。
彼は歌ふ、壮麗な天空の周辺に腰を下ろして、オルフェは!
岩は歩み、よろめき、魔の石のひとつひとつは
青空へ向かつて熱狂する新たな重荷を悟る!
半ば裸形の殿堂の躍り立つのを、夕暮れは浸し、
夕暮れは七弦琴(りら)の上、気高い讃歌(うた)のひろびろとした魂に、
おのづから黄金色(きん)のなかに集り整ふ!
我が友の蝉が啼いてゐる。蝉は、どこででも啼いてゐる。耳を澄すと、その声は、しかし、あちらからこちらへ、こちらからあちらへ、しづこころなく啼き移るやうだ。――あの木にも、この木にも、やはり長くは居つかないのか、啼き移るその声は、見知らぬ群集のなかをさまよふやうに、一声歇んで一声起る、絶え間なく啼き継ぎながら、次々に絶え入る。その声のなかに、昔の友よ! 君の声を尋ねて、私は、はぐれる。もはや聴えない、あんなに近く聴えた声が、もはや私には聴えない。――劇しく啼きしきる蝉の声に、耳を藉しながら、私は古い椅子に腰を下ろしてゐる。私の眼は大きく見開きながら、在らぬ方をさまよふやうだ。蝉が啼いてゐる。蝉は確かに啼いてゐる。蝉はどこででも啼いてゐる。空はこのとき、底の知れない暑熱を胎み、色濃く、藍に干上る。別の世界のやうに、見知らぬ世界のやうに。(菱山修三「蝉」)
《私は遅刻する。世の中の鐘がなってしまったあとで、私は到着する。私は既に負傷している‥‥》(菱山修三「夜明け」『懸崖』所収)
ある夜、私は酔ひ痴れてゐた。「チエホフの桜の園は、結局に於て尨大な詩ではないか。いはゆる詩は人間のアニマルを描いてゐない。アニマルを描きつくして顕れた大いなる詩の前では、いはゆる詩は無意味ではないか」
菱山はその夜疲れきつてゐた。私の惨酷な言葉に彼は泣きさうであつた。
翌る日、私は彼の手紙を受け取つた。
「友よ、詩の終るところに小説がある。併し、小説の終るところにも詩があるのだ」
彼の言葉は正しい。彼の詩は絶対の極点を貫き走つてゐるのだから。そして私は彼の詩をこよなきものに愛誦してゐる。わが友は日本の生んだ最も偉大な詩人の一人となるであらう。このことは、もはや私の確信となつた。(坂口安吾「宿命の CANDIDE」)