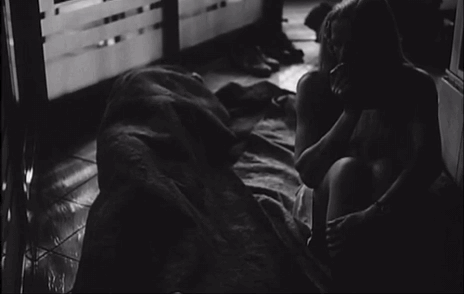以下、主にメモ。
【固有名とEinheit(差異の統一)】
言語において、固有名と「この」のような特権化された指標は、Einheit (差異の統一性、単一性:カント)の予定調和的 pre-established 形式である。それらは主体を「一」として数えcount as one、残りの叙述 proposition にふさわしい両一義的 bi-univocal な関係にとっての蝶番(旋回軸 pivot) を提供する。 (Guillaume Collett、The Subject of Logic: The Object (Lacan with Kant and Frege),2014,PDF)
【
固有名と単独性】
……私はここで、「この私」や「この犬」の「この」性this-nessを単独性singularityと呼び、それを特殊性particularityから区別することにする。単独性は、あとでいうように、たんに一つしかないということではない。単独性は、特殊性が一般性からみられた個体性であるのに対して、もはや一般性に所属しようのない個体性である。(柄谷行人『探究Ⅱ』)
【固有名と一の徴】
ラカンのセミネールⅨ(同一化)における「A は A ではない」が意味するのは、A はそれ自身と同じではない、ということだ。あるいは、よく知られたラカンの言い方なら、A は棒線が引かれている(Ⱥ)、ということである。間違えてはならないのは、A は実際には B だとラカンは言っているのでは決してないことだ。もっと正確に言えば、「一の徴 unary trait」としての文字は、「一」として counts as one 数えるが、それは一つの「一」ではない not a one、ということである。
ラカンの固有名の理論とエクリチュールの理論は、固有名の真の性質は、いかに「一の徴」としての「文字」であるかを示すことを目指している。それは、書かれた徴から分離できない。固有名は、バートランド・ラッセルによって提案された定義‘word for particulars'(個別なものを描写なしでそのもの自体として示す言葉)としては理解できない。(Lorenzo Chiesa,ount-as-one, Forming-into-one, unary trait, s1,2006,PDF)
ーーと三人の論者の文を並べたが、ここでまず、Guillaume Collettの文章をもう少し続けよう。
【「一の徴」 trait unaire と「一として数えること」compte-pour-un】
……「一の徴」は、いまだシニフィアンとなってはいない独特の印 mark である。というのは、他の諸シニフィアンとの統語的 syntactical 関係に入っていないから。「一の徴」はそれ自体、フレーゲ的な意味で、プレ数的なものである。
興味深いのは、ラカンが「一の徴」とカントのEinheit を明示的に比較していることだ(Lacan, Seminar IX. L'identification , lesson of 7/3/1962)
対象Xは、…カントが、起源の統覚、あるいは Einheit (単一性 unicity)と呼んだ超越論的主体の機能である。バディウはこれを、多様性 manifold を「一として数えること counting-as-one」と定義した。(Guillaume Collett、2014)
※フレーゲ=Guillaume Collett、2014のいくらかは、「
ゼロと縫合 Suture」を参照。
ここで、Guillaume Collettは、ラカンの 「一の徴」trait unaire (つまりは、フロイトの「ein einziger Zug」)、 バディウの「一として数えること」compte-pour-un 、カントのEinheit、あるいは超越論的統覚Xなどを殆ど同じものとしていることになる。
バディウの概念である “count-as-one [compte-pour-un]” ( 「一」として数えること)と“forming-into-one [mise-en-un]”( 「一」への形成化)は、ラカンの“unary trait” ( 一の徴)と S1(主人のシニフィアン)のよりよい理解のために有効に働きうる。この両方において問題になっているものは、構造とメタ構造、現前と再現前(表象)presentation and representation とのあいだの関係性である。(Count-as-one, Forming-into-one, unary trait, S1 ,Lorenzo Chiesa)
ーー
compte-pour-un( 「一」として数えること)については、「
反復されることになる最初の「真理」などは、ありはしない?」の末尾近くにいくらかの引用がある(仏原文のままだが)。
たとえば、
◆
compte-pour-un
«…… que toute référence au vide produit un excès sur le compte-pour-un, une irruption d'inconsistance » (Badiou, L'être et l'événement,)
◆
mise-en-un
« la mise-en-un du nom du vide »
◆
l'Un n'est pas(opération)
« Ce qu'il faut énoncer, c'est que l'un, qui n'est pas, existe seulement comme opération. »
それ以外に、ジュパンチッチのバディウ論が、あまりにも明晰ですばらしい(同じリンク先にある)。それは、次のような文で始まる。
……ラカンの公式、《シニフィアンは他のシニフィアンに対して主体を表象する》。これは現代思想の偉大な突破口 major breakthrough だった。…この概念化にとって、再現前(表象 representation)は、「現前の現前 presentation of presentation」、あるいは「ある状況の状態 the state of a situation」ではない。そうではなく、むしろ「現前内部の現前 presentation within presentation」、あるいは「ある状況内部の状態」である。
この着想において、「表象」はそれ自体無限であり、構成的に「非全体 pas-tout」(あるい は非決定的 non-conclusive)である。それはどんな対象も表象しない。思うがままの継続的な「非-関係 un-relating 」を妨げはしない。…ここでは表象そのものが、それ自身に被さった逸脱する過剰 wandering excess である。すなわち、表象は、過剰なものへの無限の滞留 infinite tarrying with the excess である。それは、表象された対象、あるいは表象されない対象から単純に湧きだす過剰ではない。そうではなく、この表象行為自体から生み出される過剰、あるいはそれ自身に固有の「裂け目」、非一貫性から生み出される過剰である。現実界は、表象の外部の何か、表象を超えた何かではない。そうではなく、 表象のまさに裂け目である。
ーーわたくしが今こうやってメモしているのも、この文に巡りあったからだ。
…………
さて、Guillaume Collettの文に、《対象Xは、…カントが、起源の統覚、あるいは Einheit (単一性 unicity)と呼んだ超越論的主体の機能である。バディウはこれを、多様性 manifold を「一として数えること counting-as-one」と定義した》とあったが、柄谷行人の解釈するカントの超越論的統覚Xとはなんだったか。以下、『トランスクリティーク』2001からである。
【自己・貨幣・アソシエーションと超越論的統覚X】
カントは……、自己は仮象であるが、超越論的統覚Xがあるといった。このXを何らかの実体にしてしまうのが、形而上学である。とはいえ、われわれは、そのようなXを経験的な実体としてとらえようとする欲動から逃れることはできない。したがって、自己とは、たんなる仮象ではなく、超越論的な仮象である。(P.24)
デカルトは、「思う」をあらゆる行為の基底に見出す。《それでは私は何であるのか。思惟するものである。思惟するものとは何か。むろん、疑い、理解し、肯定し、否定し、欲し、欲しない、また想像し、そして感覚するものである》(『省察』)。このような思考主体は、カントによれば、「思考作用の超越論的主観すなわち統覚X」である。私はこのような言い方を好まないが、カントのいう「超越論的主観X」とは、いわば「超越論的主観〔「主観」に×印を上書きする〕」である。それはけっして表象されない統覚であって、それが「在る」というデカルトの考えは誤謬である。しかし、デカルトのコギトには、「私は疑う」と「私は思う」という両義性がつきまとっており、しかもそれらは超越論的自我について語るかぎり避け難いものである。(p132)
アソシエーションは中心をもつが、その中心はくじ引きによって偶然化されている。かくして、中心は在ると同時に無いといってよい。すなわち、それはいわば「超越論的統覚X」(カント)である。(P.283)
貨幣は、たんに価値を標示するものではなく、それを通した交換を通して、すべての生産物の価値関係を調整するものだ。したがって、貨幣は全商品の関係体系の体系性として、すなわち、超越論的統覚
Xとしてある。貨幣は仮象であるとしても、いわば超越論的仮象である。それをたんに否定しても、別の形で必ず残るのだ。市場経済においては、貨幣が実体化されてしまう。すなわち、貨幣のフェティシズム、そして、貨幣の自己増殖としての資本の運動が生じる。というより、ブルジョア経済学者は、それが資本の運動の所産であることを隠蔽した上で、市場経済の優越性を論じているのだ。にもかかわらず、資本に転化するからといって、こうした貨幣による市場経済を廃止してしまえば、元も子もなくなってしまう。かといって、市場経済を認めつつそれを国家によって制御していこうという社会民主主義には、資本と国家を揚棄するという展望などまったく存在しない。彼らは貨幣を「中立化」するが、けっしてそれを揚棄することを考えないのだ。(P.435)
カントの[差異の統一性・単一性」(
Einheit)、ラカンの「一の徴」
trait unaire、主人のシニフィアン
S1、バディウの「一として数えること」
compte-pour-un などがすべて、全く同じものとするほどにはわたくしは充分に理解できていない。おそらくそれぞれ微妙な差異があるのだろう。
だが、すべて、ラカンの「ポワン・ド・キャピトン
point de capiton」(クッションの綴じ目)、あるいはミレールによって形式化されたラカンの「縫合
Suture」にかかわることはたしかだ。
【「主体の関係」と縫合】
縫合 Suture とは、主体の「言説の鎖」に対する「主体の関係」の名である。…それは、替え玉(代役 [tenant-lieu])の形式にて、欠けている要素として形象される。欠けているとはいえ、純粋に・単純に不在ではない。拡張して言えばーー「構造」に対する「欠如」の一般的な関係について言えばーー、縫合は要素の性質を持っている。それが、代役 [tenant-lieu]の場を意味する限りにおいて。(ミレール『縫合』ーーゼロと縫合 Suture)
かつまた、「
バルトとマナ(浮遊するシニフィアン signifiant flottant)」や「
クッションの綴じ目と社会的縫合」などで見たように、レヴィ=ストロースのマナ=浮遊するシニフィアンにもかかわることもたしかだ。
【ゼロと浮遊するシニフィアン】
われわれは、マナ型に属する諸概念は、たしかにそれらが存在しうる数ほどに多様であるけれども、それらをそのもっとも一般的な機能において考察するならば(すでに見たように、この機能は、われわれの精神状態のなかでもわれわれの社会形態のなかでも消滅してはいない)、まさしく一切の完結した思惟によって利用されるところの(しかしまた、すべての芸術、すべての詩、すべての神話的・美的創造の保証であるところの)かの「浮遊するシニフィアン(signifiant flottant)」を表象していると考えている。 (レヴィ=ストロース『マルセル・モース著作集への序文』)
……すべてのシニフィアン化 signifying 領野は、補充のゼロシニフィアンによって「縫合」される。《ゼロの象徴的価値、すなわち、補充の象徴的内容の必然性(必要性)を徴付ける記号、シニフィエが既に含有するものの上に覆い被さるもの》(レヴィ=ストロース)。
このシニフィアンは、「純粋状態におけるシンボル a symbol in its pure state」である。どんな確定した意味も欠如しており、意味の不在と対照的に、意味の現前自体を表す。さらにいっそう弁証法的捻りを加えるなら、意味自体を表すこの補充シニフィアンの顕現の様相は、「非意味」である(ドゥルーズが『意味の論理学』でこの要点を展開したように)。こうして、マナのような概念は、《あらゆる有限の思考から逃れ去る「浮遊するシニフィアン」以外のなにものでもないものを表象する》(レヴィ=ストロース)。ーー(ジジェク、LESS THAN NOTHING,2012より私訳)
マナ、すなわちゼロ記号である。
【マナとゼロ記号】
「ゼロ記号」は数学におけるXのように意味の不定値を表す働きをする。(……)
その独自の機能は、シニフィアンとシニフィエの間のずれを埋めること、あるいはより正確にいえば、(……)シニフィアンとシニフィエの間の相補関係が損なわれて、両者のあいだに不整合な関係が生じていることを徴づけることである。(浅利 誠「レヴィ・ストロースとブルトンの記号理論」ーー「マークつきの空虚=マナ」との同一化)
柄谷行人のゼロ記号の捉え方は次ぎの通り。
【超越論主観とゼロ記号】
……「構造」はそれを統合する超越論的主観を暗黙に前提としている。しかし、構造主義者がこうした「主観」なしにすませうるのみならずそれを否定しうると考えたのは、彼らが、存在しないが体系を体系たらしめるものを想定したからである。それが、ゼロ記号である。たとえば、ヤーコプソンは音韻の体系を完成させるためにゼロの音素を導入した。
《ゼロの音素は、……それが何らかの示差的性格をも、恒常的音韻価値をも内包しないという点において、フランス語の他のすべての音素に対立する。そのかわり、ゼロの音素は、音素の不在を妨げることを固有の機能とするのである》(R.Jakobson、……1971)。
このようなゼロ記号はむろん数学から来ている。ブルバキによって定式化された数学的「構造」とは、変換の規則である。それは形のように見えるものではなく、見えていない働きである。変換の規則においては、変換しないという働きが含まれなければならない。ヤーコブソンによって設定されたゼロの音素は数学的な可変群における単位元に対応するものだといってよい。それによって、音素の対立関係の束は構造となりうる。レヴィ=ストロースがヤーコブソンの音韻論に震撼されたのは、それによって多様で混沌としたものが秩序的であることを示すことが可能だと考えたからである。
《音韻論は種々の社会科学に対して、たとえば核物理学が精密科学の全体に対して演じたのと同じ革新的な役割を演ぜずにはいない》(『構造人類学』)。
レヴィ=ストロースは、クライン群(代数的構造)を未開社会の多様な親族構造の分析に適用した。ここに、狭義の構造主義が成立したのである。
だが、ゼロ記号とは、それ自身は無でありながら体系性を成立させるような「超越論的主観」の言い換えなのであって、それを取り除くことではない。ゼロは紀元前のインドで、算盤において、珠を動かさないことに対する命名として、実践的・技術的に導入された。ゼロがないならば、たとえばニ○五と二五は区別できない。つまりゼロは、数の「不在をさまたげることを固有の機能とする」(レヴィ=ストロース)のである。ゼロの導入によって、place-value-system(位取り記数法)が成立する。だが、ゼロはたんに技術的な問題ではありえない。それはサンスクリット語においては、仏教における「空」(emptiness)と同じ語であるが、仏教的な思考はそれをもとに展開されたといっても過言ではない。ドゥルーズは、「構造主義は、場所がそれを占めるものに優越すると考える新しい超越論的哲学と分かちがたい」(「構造主義はなぜそうよばれるか」)といったが、place-value-system(位取り記数法)において、すでにそのような「哲学」が文字通り先取られているといってもよい。この意味で構造主義はゼロ記号の導入とともにはじまったのだが、構造主義者自身はその哲学的含意について考えなかった。たんに、彼らはそのことによって、主観から始まる近代的思考を払拭しえたと信じた。だが、主観なしにすませると思いこんだとき、彼らは暗黙に主観を前提としていることを忘れたのである。(柄谷行人『トランスクリティーク』pp.119-121ーー「メタランゲージはない」と「他者の他者はない」)
これらのマナ、浮遊するシニフィアン(ゼロシニフィアン)、超越論的統覚X、主人のシニフィアンなどを、けっして超越的シニフィアンとして捉えてはならない。そうではなく、超越論的シニフィアンなのであり、それは決してシニフィアンを統括する超越神審級にあるのではなく、超越論的な場(横にずれる場、アンチノミー)にある。
物自体はアンチノミーにおいて見い出されるものであって、そこに何ら神秘的な意味合いはない。それは自分の顔のようなものだ。それは疑いもなく存在するが、どうしても像(現象)としてしか見ることができないのである。したがって重要なのは、「強い視差」としてのアンチノミーである。それのみが像(現象)でない何かがあることを開示するのだ。
カントがアンチノミーを提示するのは、必ずしもそう明示したところだけではない。たとえば、彼はデカルトのように「同一的自己」と考えることを、「純粋理性の誤謬真理」と呼んでいる。しかし、実際には、デカルトの「同一的自己はある」というテーゼと、ヒュームの「同一的自己はない」というアンチテーゼがアンチノミーをなすのであり、カントはその解決として「超越論的主観X」をもちだしたのである。(柄谷行人『トランスクリティーク』p81ーー「言い得ぬもの」はアンチノミーの場にあり、何ら神秘的な意味合いはない)
…………
さて、ここで少し目先を変えて、プルーストと固有名をみてみよう。
《固有名詞は、いわば無意識的記憶の言語のかたちである。したがって、『失われた時を求めて』の執筆を「始動」させた(詩的な)事件とは、まさに『名前』を発見したことなのである。》(ロラン・バルト『新 = 批評的エッセー』所収)
恋人同士がニックネームで呼び合うカップルを思い起してもよい。それは場合によって愛のマナとして機能する。
実際、作家が固有名詞を案出するときは、プラトンの言う立法者が普通名詞を創出しようとするときと同じ動機づけの規則にしばられる。(ロラン・バルト『プルーストと名前』)
ーーバルトは、「立法者」という言葉を出すことによって、ラカンの主人のシニフィアンや父の名概念を想起していたに違いない。
プルーストにおける「名前」は、あらゆる場合に、ただそれだけで辞書のある項目全体の等価物である。ゲルマントという名前は、思い出や慣用や文化がそこに含ませうるものをすべて、ただちにつつみこむ。(ロラン・バルト「プルーストと名前」P.81)
たとえばアルベルチーヌは、《浜辺と砕ける波》を含み、まぜ合わせ、化合させる enveloppe, incorpore, amalgame 。もはやわれわれが見ている風景ではなく、逆に、その中でわれわれが見られているような風景に、どのようにして到達できるだろうか。《もしも彼女が私を見たとして、私は彼女に何を示すことができたのか。どのような世界の内部から、彼女は私は見わけるのか。》(ドゥルーズ『プルーストとシーニュ』p.8-9)
【主人のシニフィアンと縫合】
S1はシニフィアン〈一〉から来る、その格言「〈一〉のようなものがある」(Y a de l'Un)にて。これに基づいたS1はどんなシニフィアンでもいい。こういうわけで、彼の言葉遊びS1、essaim(ミツバチの群)ーーラカンの言葉遊び、エスアム→ S1ーーがある。問題はシニフィアンの特質ではなくその機能である。一つの袋(envelope封筒)を与え、そのなかで全てのシニフィアンの鎖が存続できるようにするのだ(S.20)。 (Paul Verhaeghe,Enjoyment and Impossibility 、2006,私訳)
【超越論的マナ】
最後のラカンにとって、現実界は、象徴界の「内部にある」ものである。Dominiek Hoensと Ed Pluth のカント用語にての考察を捕捉すれば、人は同じように、最後のラカンは現実界の超越的概念から、超越論的概念に移行した、と言うことができる。 ( Lacan Le-sinthome by Lorenzo Chiesaーー超越論的享楽(Lorenzo Chiesa))
【原抑圧と一の徴】
ーーーラカンセミネールⅨ『同一化』より
さて、現実の機能が知覚の機能に結び付けられているこの世界においてはやはり思考の同一性という道によってしか知における進歩を望むことはできない。このことはわれわれにとって逆説ではないが、逆説的なのはフロイトのテクストにおいて、無意識が探し求めるもの、無意識が欲するもの、無意識の活動の根底にあるものは知覚の同一性であるということを見出すことである。このことは次のことを意味しないならば文字通り何の意味もないであろう。つまり、無意識と自らの固有の回帰様式において無意識が探し求めるものとの関係は、まさに一度知覚されたものがまったく同一なものとしてあるということ、その時の知覚、たとえば一度指輪を通したときの最初のあの感覚を取り戻すということなのである。そしてそれはまさに永遠に失われたものなのである。というのは原初のシニフィアンに答えるすべてのものの再出現には、このシニフィアンを代理表象するものが何であれ、 原初のシニフィアンの最初の出現の唯一の印trait unaireが欠けているであろうからである。
原初のシニフィアンは、問題になっている原抑圧のなにかが無意識的存在、無意識である内的秩序における反復的主張に移行する瞬間に一度現れるのである。主体は外世界から何かを受容し、そしてそれを拘束しなければならず、それを拘束するにおいてシニフィアン的形態で拘束するゆえにその差異しか受容できないのである。それゆえに、無意識の主体を特徴づけるのは知覚の同一性の追求であるが、主体は知覚の同一性の探求に満足を得ることができないのである。 (ラカン、同一化、向井雅明試訳)
《固有名は、本来の象徴的なものというよりは、文字にいっそう近い。固有名は、「一つの徴」に接近する。その操作 operation を繰り返すことにより。そのカウントの内-差異を繰り返すことにより。そして、このようにして、言語構造、シニフィアンの差分的音素の鎖の一貫性を支える。》(Lorenzo Chiesa、2006)
ーーここにある操作 operationという言葉に注意をしておこう。
バディウ、Badiou, L'être et l'événementより。
« Ce qu'il faut énoncer, c'est que l'un, qui n'est pas, existe seulement comme opération. »
« un pur ‘il y a' opératoire »
…………
※附記
【サントームと縫合】
ラカンの晩年のサントーム概念も主体の縫合にかかわる。
Pourquoi est-ce qu'on n'inventerait pas un signifiant nouveau? Un signifiant par exemple qui n'aurait, comme le réel, aucune espèce de sens?” ( J. Lacan, Le Séminaire XXIV, L'insu que sait de l'une bévue, s'aile a mourre, Ornicar ?, 17/18, 1979, p. 21)
《なぜ我々は新しいシニフィアンを発明しないのか? たとえば、それはちょうど現実界のように、全く無意味のシニフィアンを》とでも訳せる文だが、この新しいシニフィアンがサントームである。かつまた、ラカン流のエディプス理論であり(参照:
エディプス理論の変種としてのラカンのサントーム論)、敢えていえば、紆余曲折した上での最晩年のラカン理論のマナである。
精神分析実践の目標は、人を症状から免がれるように手助けすることではない……。正しい満足を見出すために症状から免れることではない。目標は享楽の不可能の上に異なった種類の症状を設置 install することだ。(PAUL VERHAEGHE,new studies of old villains A Radical Reconsideration of the Oedipus Complex,2009)
《サントームsinthomeとは、最近、症状symptômeと綴られるようになったものの古い書記です。》(ラカン、セミネールⅩⅩⅢ)
かつまた、サントームは、音の上では saint homme : 聖なる人間,つまり聖人と同音である。そして、さらには、聖トマスSaint Thomas をも想起させる(ポール・ヴェルハーゲ)。聖トマスとは、〈大他者〉――キリストーーを信ぜず、独自の道を歩んだ者だ。
これだけではなく、たとえばsin-homme(罪の人)、synth-homme,(模造人間、人工的に自己-創造した人間)などを提示する論者もいる。
ーーどうして、これらの語彙群から、サントームをマナ(ラディカル化されたマナ)としていけないわけがあろう(
参照)。しかも、サントームという語自体が、浮遊するシニフィアンである(バディウ曰くの、多様性 manifold を「一として数えること counting-as-one」だ)。
…………
※参考
「この私」における「この」は、何も指示しない。それにしても、「この」は何かを指示するといわねばならない。それはたんに私と他者の差異(非対称性)を指示するのだ。というより、この差異が他者を他者として、私を私としてあらしめるのである。(柄谷行人『探求Ⅱ』「第一部 固有名をめぐって」P.18)
象徴秩序(「他」)、主人のシニフィアン、ファルスのシニフィアン、「一」One を同じものとするラカンの考え方は、読者には不明瞭かもしれない。私は次のように理解している。
システムと しての象徴秩序(「他」)は、差異をもとにしている(ソシュール参照 )。差異自体を示す最初のシニフィアンは、ファルスのシニフィアンである。したがって、象徴秩序は、ファルスのシニフィアンを基準にしている。それは、一つのシニフィアンとして、空虚であり、(例えば)二つの異なるジェンダーの差異を作ることはない。それが作るのは、単に「一」と「非一」である。これが象徴秩序の主要な効果である。それは二分法の論法ーー「一」であるか「一」でないかーーを適用することによって、一体化の形で作用する。……(ポール・ヴェルハーゲ、2001,私訳)
柄谷行人は、固有名が、何も指示しないが、「
私と他者の差異(非対称性)」を指示する、としている。
ヴェルハーゲは、ファルスのシニフィアンは空虚であるが、
「一」と「非一」を作る、としている。
ーーラカンの象徴的ファルスや父の名、主人のシニフィアンS1は、少なくともある時期から(セミネールⅥ以降から)、同じものである(参照:
父の名、Φ、S1、S(Ⱥ)、Σをめぐって)。
象徴秩序という「他」 l'Autre」を「一」l'Un の介入によって、私と非私を作るのが、(まずは)固有名、あるいは「私」という主人のシニフィアンの機能であるといってよいだろう。
……「私」といい「世界」といっても、真実は「私/世界」という、不可分のものを指しているのである。それは、ウォーコップ/安永浩のいう意味における「パターン」である。不可分なだけでなく、「私」があって「世界」があるのであり、「私」という概念が「世界」に優先する。「非-私」として「世界」を定義することは可能だが、「非-世界」として私を定義できない。(中井久夫「「世界における索引と徴候」について」『徴候・記憶・外傷』所収 p.26)
ラカンはセミネールⅩⅦの冒頭近くで、主体が発生する以前に存在する S2 を語っている。
Nous considérons désignée par le signe S2 la batterie des signifiants, de ceux qui sont déjà là.Car au point d'origine où nous nous plaçons pour fixer ce qu'il en est du discours… du discours conçu comme statut de l'énoncé …S1 est celui qui est à voir comme intervenant, intervenant sur ce qu'il en est d'une batterie de signifiants que nous n'avons aucun droit, jamais, de tenir pour dispersée, pour ne formant pas – déjà - le réseau de ce qui s'appelle un savoir.
一見、中井久夫の叙述と違和があるようにみえる、--《「私」があって「世界」があるのであり、「私」という概念が「世界」に優先する》。だが、中井久夫の表現は、鉤括弧による「私」であり、主体のことだ。誕生後の乳幼児は、いまだ「私」ではない。
これをポール・ヴェルハーゲは、英訳のセミネールⅩⅦの解説文(2006)において、ほぼ次ぎのように解説している。以下、摘要であり、仏語をつけ加えたり要約したりしている。
主体の発生以前に、世界には既に S2(シニフィアン装置 batterie des signifiants)が存在している。S2 に介入するものとしての S1 (主人のシニフィアン)は、しばらく後に、人と世界のゲームに参入するが、そのS1は、主体のポジションの目安となる。この S1 の導入とは、構造的作動因子 un opérateur structural としての「父の機能」 la fonction du père のことだ。S1とS2 との間の弁証法的交換において、反復が動き始めた瞬間、主体は分割された主体 $ (le sujet comme divisé )となる。(ポール・ヴェルハーゲ、 Enjoyment and Impossibility、2006).